|
作曲家佐藤慶次郎の音楽と思想
山梨大学名誉教授 中嶋恒雄
1 はじめに
本稿を私が執筆する事情について、まず述べて置きたい。私は、佐藤が28歳の1955(昭和30)年の
初夏に、初めて彼に出会った。私が作曲家を志望し、大学受験のために通っていた予備校を中退した
ために、青山でピアノの専門店を営んでいた父が心配して、知己である佐藤に引き合わせてくれたか
らである。以後、私の東京芸術大学在学中から彼の死に至る半世紀以上にわたって、佐藤は私の父親
以上に、身近な存在であった。佐藤は世の音楽家たちのように、謝礼を取って弟子を教えるというこ
とを考えもしなかったから、私が彼に師事したというのは当たらない。しかし私は彼をずっと先生と
呼んできたし、同じ作曲の道の偉大な先輩、或いはまた偉大な兄のような気持ちで彼に仕え、人生の
指針としてきた。彼もまた私を、親しい後輩、或いは自ずから面倒をみるべき年下の友人として遇し
てくれた。従って彼の死後、彼の残した厖大なノートは当然のように、和子未亡人から私に託され
た。これらのノートには、彼の日々の思考、作曲やオブジェ制作のプラン、手紙や執筆物の下書き、
外国語文献の翻訳、実生活での私的な感慨等々、彼の人生のほぼ全ての記録が残されている。そこで
私が彼の音楽上のただ一人の弟子として、ノートを解読しながら彼について執筆することを、ご理解
頂きたい。佐藤慶次郎はエレクトロニック・アートと作曲の二つの分野で仕事をした。このまったく
異なる二つの分野には、彼独自の広大な思想的背景が横たわっている。彼は、自分の思想を深めるた
めに、また制作のプランのために、上述のようなノートを残した。彼の思想は、禅仏教と関わり、
アートは電磁的な知識や造形や色彩と関わり、作曲は1945年以降の前衛音楽のあり方と密接に関係を
持っている。従って一人の研究者が、ノートのすべてを読み解くことは、非常に困難である。そこで
ここでは、作曲とそれに関わる思想的背景にのみ、主題を限定して述べよう。彼はこのように関心の
領域を広げたが、彼の心底にはつねに、自分は作曲家であるという規定があった。そこでたとえ私
が、彼の思考の三分の一の領域にしか光を当てることができないとしても、彼を理解して頂く材料と
しては、その半分くらいを提出できるかと思うからである。
佐藤の楽器のための作曲の仕事は、1954(昭29)年の日本の音楽家の登竜門である毎日・NHK音楽コ
ンクールに応募して2位に入賞した「ピアノとオーケストラのためのレントとアレグロ」の創作か
ら、1965(昭40)年に岩城宏之指揮NHK交響楽団のメンバーによって初演された「10の弦楽器のための
カリグラフィー第2番」までのわずかに10年と少しの間しかなされていない。そして65年から71年ま
での6年間は、電気的な音響システムを使う環境音楽、或いはサウンド・ディスプレイのような音響
システム全体の制作へと進んで行き、1972年からは、音楽の領域からアートの領域へと、創作分野を
完全に変更してしまった。彼は慶応義塾大学医学部に入学する以前から、詩を書いており、大学在学
中に作曲家早坂文雄に師事して音楽を始めてから、わずかに7、8曲を発表したのみで、音楽を中止し
てしまったのである。この辺の事情を友人であった武満徹は、「佐藤が音楽にもとめた純粋性は、結
局、詩とか音楽とか、一見純化された様式を通しては実現されないものであることが、私は自分の事
のように理解できるのである」(注1)と述べたのであった。それでは佐藤が音楽に求めた純粋性とは何
であるのか。これを明らかにすることが、本稿の眼目となるであろう。
2 詩作から作曲家への道
佐藤は、第二次世界大戦戦時下の少年期から青年期への移り変わりの時期に、父親の郷里長野県高
遠の疎開先において、詩を書いていた。残念ながらこれらの詩作品は、上のノート群の中に見つける
ことができなかった。ただ1編私たちに遺された詩は、昭和23年7月に発行された同人詩誌「形象」
に発表され、後に復刻された「訣別」と題されたもののみである。
訣別
--昭和19年某月某日 叔父ネグロス島にて戦死す--
ネグロス島、藍色に暮れなずむ 青い丘辺に立って、あなたは別れのハンカチを振る。
日本を発(た)つ時 見知らぬ人々が あなたにした様に
窪んだ平地の 靄の底の
ひとすじけむり立つ 侘しい聚落(しゅうらく)に向かって、
水平線のあなた
くれない燃える 雲片(くもぎれ)のかなたに向かって、
あなたは最後のハンカチを振る。
さようなら 日本{ハイマート}
妻よ、児(こ)等よ、
愛したすべての人々よ、
めぐりあはなかった もろもろの人々。
さようなら
もう、再びねがふこともない
人生の悦楽よ
私の数々の 束の間の 人間の苦悩のにじむ
此のハンカチのみを地上に残し、
肉体、魂と共に
今は虚しく 此の丘に潰え去る。
さようなら
愛するすべての人々よ。
再びめぐりあふこともない 人生よ
やがて日が暮れるまで あなたは
過ぎ去った諸々の思想(おもい)を、
人間の心に向かって
淡い灯{あかし}の様に 振りつづける。
このただの1編から、佐藤の詩を云々することはできない。けれども彼を長い間見つめてきた和子
夫人はもちろんのこと、彼に身近に接した者にとっては、この1編からでも彼のあり様を、心に浮か
べることができる。妻も子も持たない青年期の佐藤が、妻子を残して死ななければならない立場に置
かれた年長の人間の心を思いやる事のできる能力、未だ見た事もない南の島の色彩や地形をイメージ
する能力、さらには「くれない燃える 雲片{くもぎれ}のかなた」のような表現に見られる、自然の
事物への感性のよさなど、これらは後に具現化した「ピアノのためのカリグラフィー」や、オブジェ
「すすき」のような作品の基盤となる彼の心の働き方に通底するもの、と云うことができる。ちなみ
にここで読まれた叔父は、彼の母の弟であり、彼の通った慶応商工学校の教諭であった。音楽を愛
し、彼にSPレコードを買い与え、英語を教えたという。詩作の初歩を導いたのもまた、この叔父で
あった。この叔父は英語ができることで第2次大戦下において軍に徴用され、南の島で戦死したので
あった。また彼は、幼い頃すでに暮れなずむ夕空を見上げながら、「ここは僕の居場所ではない」と
感じたと云う。この感覚を別のノートでは、「何か所を得ていない」、或いは、「僕は医学をやって
も、詩を書いても、いつも空虚さにつきまとわれていた」とも述懐している。私にはこのことを、時
に「違和感」という言葉で話してくれたのだが、これらのノートを読むことの許された今初めて、こ
の感覚の超克こそが、彼をして彼の人生を歩ませたのだと、納得がいくのである。この無常観ともい
うべき彼の根源的な感覚は、「さようなら 愛するすべての人々よ」という言葉の中にも、当然のこ
ととして潜んでいる。佐藤は詩作について、次のように書いている。「僕は、自分の詩が説明的な要
素を持つことを極端に嫌い、次第に抽象化の傾向を辿った。純粋なイメージの結合によって、感覚を
直接的に捉えるものを作りたいと思ったのだ。僕の試みは満足できる結果に到らなかったが、結局、
僕は言葉で音楽を書こうとしていたのだった。それは音で実現すべきものだったのだ」。この経過の
必然の成り行きとして、彼は和子夫人の母堂の紹介で、前衛作曲家で映画音楽でも知られた早坂文雄
に師事することになった。しかし早坂と佐藤の関係は、私と佐藤の関係と同じ様なものであった。早
坂は、作曲は教えられるものではないから弟子は取らない。だが作品を持って遊びにくるのはよい、
と云ったという。ここから佐藤の作曲家人生がスタートした。時に、佐藤22歳1949年2月21日であっ
た。
1955年に発表された「ピアノのための5つの短詩」、器楽アンサンブルのための「コンポジショ
ン・モノジェニック」の発表に至る、1949年から6年間の佐藤の作品は15曲あり、毎日・NHK音楽
コンクール入賞曲1曲を除いて、すべて未発表のままに草稿が残されている。作曲初歩の学習経験も
なく、作曲界の動向も知らず、早坂の名さえ知らずに作曲を始めた佐藤にとって、「僕は習作を書こ
うというのではなく、僕の持っているイメージを音で表現したかった」という思いとは裏腹に、その
実現は非常に困難なことであったろう。しかしとにかく、作曲は始められたのだ。佐藤の作品草稿の
うちで最も古いものは、50年1月27日の日付けをもつ「Andante Doloroso」と題されたピアノ曲で
ある。この曲は70小節ほどの長さを持ち、嬰へ(Fis)音を主音とする調で書かれている。上声部に主音
のオスティナート(持続音)があり、低声部で息の長い主旋律が歌われる(譜例1)。旋律は基本的には嬰
ヘ(Fis)短調に属するが、音階の第3、第6音に長短3度、長短6度を交代させ、転位音として第2音
の下降変位を使用するなどの工夫によって、悲痛な感情が表出されている。ただしこの曲の欠点は、
音楽理論上冒頭の低声へ(F)音は、嬰ホ(Eis)に書かれるべき音であり、2小節目の低声変ロ(B)音は、嬰
イ(Ais)に書かれるべき音であるなどの記譜の問題である。また草稿は、ぺん書きのところと鉛筆書き
のところが入り交じり、いまだ完成には到らなかったことが窺われる。しかし和声においては、3度
和音を避けて4度和音や空虚5度が使用されるなど、佐藤の日本的、或いは東洋的とも云うべき響き
の傾向が、はっきりと記されている。次いで古い日付けを持つ曲は、50年6月2日付けの「Allegro
for piano」である。これは稚拙な鉛筆書きではあるが、早くも後の曲に見られるような、長3度離れ
た関係を持つ、複調で書かれている。
続いて、50年10月23日の日付けのある歌曲「TOKAGE」がある。この曲は鉛筆書き、見開き2頁
の短いものである。またもう1曲、「TOKAGE」と同じ5線紙を使用した見開き2頁、鉛筆書きの日
付けのない室生犀星の詩による歌曲「寂しき春」がある。「TOKAGE」は5音の日本旋法を使った狭
い音域の歌声部に、ピアノの伴奏部は、歌声部と同じ旋律を重ねた上声部に、内声部のリズム音と4
度和声を低声に置いた、単純なものである。また「寂しき春」は、イ短調の歌声部に機能的西洋和声
の分散和音の付いた、極めて平凡なものである。いつのことであったか佐藤は私に、「早坂さんから
『あなたはこれで良いのですか』と叱責された」と語ったことがあった。恐らくそれは、これらの2
曲についてであったのかも知れない。しかし佐藤としては、先の「Andante Doloroso」で見つけた
日本風な響きと西洋風な響きを、それぞれ単独にシステムとして使用したらどういう曲になるかと、
試しただけであったのだと思う。実際、佐藤が作曲を始めてから1年ほどの歳月は、試行錯誤の連続
であった。大学医学部に通いながらの作曲活動においては、和声学の書を開いての独学から、西欧伝
来の3和音機能和声体系の響きが、佐藤の内的音楽感性には呼応しないこと、また、より自分の感性
に合致した響きを得るためには、日本的5音音階のシステムから、さらに先に進まなければならない
ことを理解しただけでも、良しとすべきであろう。
この後「1950-1951」と日付けられた「Allegretto for Piano」と、日付けのない「Improvisation」
の2つのピアノ曲が続く。ここでは前の2つの歌曲の試行の結果から、東洋的な5音音階の響きを保
ちながら、より前衛的な複調の響きが試みられる。前者は、へ調とイ調が重なりながら始められ、後
者は、ロ調と変ホ調が重ねられて構成されている。ここで特徴的なことは、前者までの楽譜が未だ稚
拙な筆使いで書かれていたのに比べて、後者では、すでに後年の佐藤の自筆譜にあるような、端整
で、強く美しい筆致が見られることである。1951年に日付けられた曲には、他に「Sonate for Vn.
and Pf.」という曲もあるが、これは3楽章Rondo(ロンド)の比較的に長い楽章と書きかけの2楽章の
草稿があるのみで、完成には至らなかったようである。1952年の日付けをもつ草稿は、「Kari no
Tsunobue」と題された、わずかに20小節の短い歌曲が1曲あるのみである。この曲は、「角笛 風
のさなかに 声は死にゆく」という作者名が記されていない詩に、ピアノ伴奏によって付曲されてい
る。しかし恐らくこの詩は、佐藤の自作であると思う。何故ならば52年に佐藤は父の死に直面し、佐
藤がつききりで看病したことが分かっているからである。そしてこの年に作品が1つしかないの
は、52年は医学部の卒業期であり、卒業試験などで忙しかったことであろうし、また卒業後に胃穿孔
のために入院、手術、療養と続いたのであるから、生きるだけで精一杯であったというのがその理由
であろう。
さて1953年になると、彼にしてはがぜん多作となる。まず「The Dance of a Buffoon(道化師の踊
り)」と題されたスキップリズムと3連音符の軽快な動機を持つピアノ曲が、完成された筆致で書か
れ、53年1月22日に日付けられている。この曲は「誕生日の余興のために」と英語の副題を持ち、結
婚1年まえの和子夫人(1928.1.23生)のために書かれたもの、と推定される。しかし和子夫人に確かめ
たところ、「献呈された覚えはない」ということなので、多分演奏が難しいために、演奏されないま
ま放置されたのだと思う。この曲では、短2度の進行や重なりが多用されており、後に続く「ピアノ
とオーケストラのためのレントとアレグロ」の動機や、一連の「カリグラフィー」へと続く、短2度
堆積の音程感覚が、確立されつつあることが窺える。次の「La pluie du printemps」(春の雨)と題さ
れたピアノ曲は、1953年2月16日と記されている。3度堆積の4和音に伴奏づけられたイ調のたおや
かな旋律動機と、3度堆積4和音を上下の5度と4度に分配した動機の交代する完成された曲で、彼
がすでに作曲家として立っていることを証明するものである。また「A fairy is dancing in the
woods」及び「Snow is dancing」と題された短い4手のピアノ曲もあり、 これらの曲は、2月20日
と2月21日の日付けを持っている。恐らく、このような一連の曲から早坂は、彼の音楽能力の非凡な
ることを認め、誰か他の人に佐藤の存在を告げたのであろう。この年の春には、今日、日本を代表す
る国際的作曲家となった若き日の湯浅譲二と日本伝統音楽の研究者となった福島和夫の両名が、彼ら
が前年に立ち上げた芸術家集団「実験工房」の仲間として、入会を勧めに来たのである。残りの未発
表草稿のうちの1曲は、53年10月23日付けのピアノ曲「Nocturne」であり、他は日付けのないピア
ノ曲「Lento」、及び1953年6月6日に日付けられたピアノ曲「Lento」である。しかしこの2つの
「Lento」は、内容をまったく異にする。前者は「ピアノとオーケストラのためのレントとアレグ
ロ」の先触れとなるものであるし、後者は、1955年に発表する「5つの短詩」へと繋がるものだから
である。この6月6日の日付けをもつ「Lento for Piano」のインクで書かれた最後の頁には、鉛筆
書きで「5つの短詩」第1曲の音列が書かれている。この「Lento」は、未だ上声部の旋律にたいし
て、低声部和音伴奏という伝統的なピアノの様式の中で書かれているけれども、旋律の1音1音を係
留して、余韻を残しながら和声的な響きを作る書法、すなわち「5つの短詩」の第1曲や、「ピアノ
のためのカリグラフィー」へと続く、佐藤独自の手法が見られる。
1953年の後半は「力がつくから大きな作品を書いたらどうか」という早坂の勧めに従って、佐藤は
「ピアノとオーケストラのためのレントとアレグロ」を書き始める。この2楽章のピアノ協奏曲とし
て構想された曲の遅い楽章レントは、弦楽群で始まる4分の3拍子の主要動機(譜例2)と、それに応
答する木管部の動機(譜例3)が組み合わされて構成されている。ピアノは初めは和音でリズムを刻む
だけであるが、オーケストラの主要動機を引き継ぐと、すぐに続いて応答動機を発展させながら、カ
デンツァの独奏部となる。独奏部はやがて弦の5音音階によるトレモロの伴奏に乗りながら、木管部
と応答動機を掛け合う。この木管とピアノの掛け合いの部分は、弦楽部の主要動機に導かれて、再現
部を作る。恐らく、毎日コンクール応募条件のための時間の制約があって、レントは、このようなカ
デンツァの中間部を挟む、単純な3部形式に設計されたものと思う。全体の垂直的な和声構造は、す
でに得た長3度離れた調を重ねる複調の手法によりながら、ここでも後の「ピアノのためのカリグラ
フィー」へと繋がる2つの短2度を重ねた、鋭く、力強い和音が鳴り響く。2楽章のアレグロは、冒
頭の主要な2つの動機(譜例4-1,2)と、中間部に現れる動機(譜例5)、及びその発展動機(譜例6)が様々
に組み合わされながら、絢爛たる表現がなされている。結果としてこの曲は、1954年度毎日・NHK
音楽コンクール作曲部門管弦楽の部の2位を受賞した。しかし、本選の演奏指揮を担当した私の指揮
の師の山田和男(一雄)は、後に大変な難曲だったと私に語ってくれたので、当時のオーケストラの
水準では、十分な演奏効果を発揮出来なかったであろうと、私は推測している。ところでこの曲に関
して、もう一つのエピソードを加えよう。私が東京芸術大学の学生の頃、ピアノで同門の年下の女子
学生がいた。彼女は、和子夫人が家庭科の教諭として勤務していた中学校に通っていた。そこで何か
の機会に、彼女たちが編集したクラス雑誌を見せてもらうことがあった。その中には「今までで先生
方の一番うれしかったこと」と云うアンケートの項目があり、和子夫人が「主人が毎日コンクールに
入賞したこと」と述べておられるのを読んだ。恐らく、毎日コンクール入賞の1月後に結婚を控えた
和子夫人にとって、佐藤のコンクールの入賞は本人以上に喜ばしい贈り物であったのだと、私は印象
深く覚えている。当時の毎日・NHK主催の音楽コンクールは、今日のように様々なコンクールがある
時代とは異なり、楽壇への登竜門として十分な権威を備えていた。そこで佐藤はこの入賞によって、
社会的にも作曲家として立つことが可能となり、以後、ラヂオ放送の背景音楽や、サウンド・ディス
プレイなどの仕事によって、収入を得る道が開けたのである。
3 「ピアノのための5つの短詩」
「ピアノのための5つの短詩」の全5曲が発表されたのは、1955年7月である。1953年中に作られた
作品は、5つのうちの第1曲と第2曲である。残念ながら5つの短詩の自筆譜には、1953年とあるの
みで、何故か日付けが記されていない。1977年に若い演奏家によって再演された機会に、佐藤は「作
曲を始め、自分の響きと方法を模索して、おぼつかない指先で音の世界を手探りしつつ、ようやく自
分自身のリアリティに行きあたったという思いを持つことのできた最初の作品が、この短詩の第1番
でした。初めから『5つの短詩』として構想されたわけではなく、実験工房に参加し、室内楽作品発
表会で発表することになって、『5つの短詩』とすることが意図され、5番、4番、3番の順に創ら
れたのでした。室井摩耶子氏によって初演され、翌年、園田高弘氏によって再演されました」(注2)と
述べている。残されたノートのうちのごく古い日付けを持つ、54年10月18日から書かれた「作曲に関
するメモ」に、「Poem3 12音の音高を限定するか、單声にすべきか」とあるから、全5曲が完成
するまでには、54年の後半か55年の始めまで、1年半ほどの月日がかけられたと見るべきだろう。同
時に発表された「コンポジション・モノジェニック」は、55年6月1日と記された古びた「作曲に関す
るノート」に、詳細な構想が残されている。従ってこの曲は、時間的には発表のかなり間際まで、作
曲されていたと思われる。
「5つの短詩第1番」は、佐藤の響きを求めての試行錯誤と彼の内なる耳との対話の結果、自然発生
的に生まれた、12音の音列(セリー)によって作られている。その音列は、他の作曲家たちがしばしば
陥ったようにただ機械的に並べるのではなく、佐藤の感性に従いながら、かなり自由に扱かうことに
よって、詩的な抒情性を生み出している。また音列それ自体が、たった12の音だけであるにもかかわ
らず、美しい動機的素材となっている。その結果、「12音による音楽は、非人間的である」とする当
時の音楽界の評価を、見事に覆したのである。それでは彼がセリーをどのように扱ったのであるか、
始めの部分を分析してみよう。
まず冒頭のこの曲(譜例7)の主題とも云える3音ずつ2つの下降する動機は、譜例8の12音の音列か
ら出来ている。佐藤はその当時、詳細に研究していた12音楽派の作曲家ウェーベルンについて、1951
年10月6日の日付けで「Webernを分析することにより、彼の作曲上のアイデアや巧緻な構成のみに
心を奪われてはならない。彼が追求した音楽の実体、音楽概念の革命に注目しなければならない」と
ノートに記している。ウェーベルンが追求した12音音楽は、どのようなものであったろうか。それは
音列の断片によって組み立てられた無調の動機が、短い休止を挟みながら変形され、モザイクのよう
に並べられながら全体を形作る。伝統的な音楽が調性という音楽的小宇宙の中で、引力のように働く
中心音からの飛翔と回帰によって、心理的な緊張と弛緩を生み出したのとは異なり、ここでは、音高
とリズム、強弱、音色によって作られる心理的な音楽空間内の造形のみが、手段となっている。音高
とリズムを持って作られる動機は、伝統的な音楽が沢山の音を使用して作りあげたのに比べると、
ウェーベルンは、ただの2音か3音でそれを作る。これらのあり方については、絵画における具象と
抽象に比べて、しばしば論じられる。しかし音楽はたとえ伝統音楽であってさえも、自然の具体物に
依ったものではないから、これはあくまでも、一つの比喩にしか過ぎない。が、この比較によってそ
れらの差異のイメージは、持つことが出来るであろう。さてこの佐藤の音楽は、ウェーベルンの12音
音楽が透明で固い物体を並べたように無機的に響くのに比べると、抒情的に歌う旋律の部分と、力強
い筆の迸りを感じさせるような気迫に満ちた音形の部分とが、必然的な対比をなして作られているの
が分かる。いま、分析の便のために冒頭の主題の音列をオリジナルとすると、次の旋律は、オリジナ
ルの音列を長2度上に移高した音列によって作られている。この2つの旋律によって主題が提示され
ると、対比的なリズムの細かく速い動機は、最初の6音がオリジナルを短2度上に移高した音列の逆
行型( 譜例9-1) 、次の6音がオリジナルの転回型( 譜例9-2) の前半を、短2度下に移高した音列によって
作られている。楽譜3段目の始めの音形は、オリジナルの転回型を長3度上に移高した音列( 譜例
10-1)の、前2音と後ろの2音が組み合わされている。そして次の音形は、オリジナル転回型完全4度
上の移高音列( 譜例10-2) の、前2音と後ろから3番目と4番目の音が組み合わされている。段落最後
の4分音符と付点2分音符の和音は、オリジナルを短2度上に移高した音列の、後ろの2音を中声部
に、前の2音ニ( D) 、変ニ( Des) をそれぞれ低声部と上声部に配置したものである( 譜例11) 。また和声
は、旋律を作る各音が適宜掛留されて作られている。このように分析してみると、佐藤が12音の基本
技法を守りながらも、彼自身の感性に従って柔軟に音列の各音を取捨選択し、使用していることが理
解できる。
「ピアノのための5つの短詩」のうちで特に特徴のある曲は、第5番(譜例12)である。これは当時の
一般的音楽通念からは、「これが音楽?」或いは「これも音楽?」というものであったろう。ここで
は譜例13の12音の音列が即興的な自由度を持ってゆっくりと提示されると、引き続いてオリジナルの
転回型(譜例14)を3音づつのグループに区切り、それらのグループa,b,c,dの4つが、b,a,c,dの順序で
現れる。ただし各グループの中では、音の出現順序は変更されている。また曲の最後に現れる短い8
分音符、ド( C) とレ( D) の音は、12音列の3番目と4番目の音が選択されたのものであろう。この音列
を3音づつのグループに区切って、それらグループ内の音の順序を変更しながら自由に使う方法は、
次の「ピアノのためのカリグラフィー」において、徹底的に開発されることになる方法の、先駆けと
なるものである。また、ここでもし普通の音楽の形式を、散文と見立てるならば、この曲は俳句のよ
うに短い形式の音楽である。佐藤はこの簡素な音だけで、自分のイメージする世界を表現したかった
のだと思う。ちなみに、この年の10月には亡くなる師の早坂がこの実験工房演奏会に来会し、友人の
作曲家大築邦雄に当てた葉書で感想を述べている。「連中の仕事は4人とも頗る調子の高い仕事で、
とてもかなわないと思いました。中でも鈴木がいっとういい境地でした。湯浅の雅楽、能の現代化も
頗る同感、武満は音色に新境地あり、佐藤のピアノも点描処理でメカニックな抒情あり。いずれも私
などより数等先を歩いておりますね。彼等が順調に伸びてくれれば、日本の作曲界も世界の仲間入り
ができることでしょう」。
4 「ピアノのためのカリグラフィー」
佐藤の作曲家としての名声を決定的にしたのは、この「ピアノのためのカリグラフィー」(譜例15)
という6分半ほどの長さを持つ作品である。曲は、3年余りの歳月をかけて1960年の夏頃に完成した
が、発表する当てもないままに女流ピアニスト田辺緑に依頼し、練習を始めたのであった。しかし、
練習は思うようには進まなかったのであろう。佐藤が田辺に当てた、練習について述べた手紙の下書
きが、ノートの間に挟まって残されている。「Calligraphieの演奏をお引き受け下さって有り難う。
演奏の機会も未定のものですし、ほんとうに心から感謝しています。私がこの作品の演奏に関して申
し上げていることは、あまりに一般的で当たり前過ぎるとお考えかも知れません。しかし『当たり
前』という言葉を媒介として、どれほど確かな了解が人間の間に成り立つものでしょうか。『当たり
前だ』という言葉は、事によっては意志疎通を確かめる便利な言葉ではあるけれど、多くの場合、人
間同士の真の理解を妨げる隔てとなっているように思われます。
さて私の作品の演奏に気力が不可欠だとか、積極的な没入を希望するとか、音と一体になるようにな
どと云うことは、演奏に関する一般的な事柄であるばかりではなく、人間の生き方の問題でもあるの
です。人間が真に生きるということは、行為そのものになることだと思うのです。それこそが人間の
究極的な在り方だとおもうのです。私が創作するとき、私は創作行為そのものでありたい。見る自分
と見られる自分が一つになった地点で、すべての音の高さや、アタック、強さを決定したい。そこで
こそ、純粋な生命力を音として充実することが出来るに違いない。私はそのように努め、たった一音
の位置を決定するために、数ヶ月を費やすことも致しました。すべての音に意味を与え、生きた関係
で結びつけることができたと信じられた時、私は筆を措いたのです。だから別の人が、再びその意味
を見出す事は必ずできる筈だと思うのです。私は数学的な関係としての美しさをそのまま音楽にすり
替えてしまう態度を、一種の詐欺的行為だと思いますが、音相互の物理的関係への配慮なしで
は、constructionは成り立たないし、音楽的存在を創り出すこともできません。このような私の態
度、絶対的現在の点で、vitalityを音にするという意図を満たすために、システマティックな方法を予
め十分に検討してから、私はピアノに向かったのです。ただ音の関係がもたらす感動ということにつ
いて考えれば考えるほど、すべての(音の要因の)決定には、論理よりも自分の感性を尊重せざるを得
なくなります。Calligraphieの意図、また世界がこのような事実を基盤として成り立っていることか
ら、『気力』『積極的な没入』『音と一体になる』などと申し上げる私の言葉は、一般的で当たり前
なことではなく、演奏に関するノートとしては、むしろ特殊に属すのではないでしょうか。あなたの
生の持続がそのまま音楽的持続となるとき、そのときあなたは音になる。あなたは音と一体になると
いうよりも、あなたが音になり、それ故、すべてのアタックが生きたものになり、音楽的必然に生命
を与えるのです。そして私とあなたのコミュニケーションが成り立つのです」。
1961年1月31日ようやく機会を得、東京千代田区三番町にあるイタリア文化会館で開催された現代
音楽コンサートにおいて、田辺緑の演奏により「ピアノのためのカリグラフィー」は初演された。そ
の夜のプログラムにはアメリカの批評家ヒューエル・タークイが、次のように書いた。「佐藤氏の最
初の作曲はピアノ協奏曲だった。それは毎日音楽コンクールの2位を受賞しNHKから放送されたが、
その後まもなく、『数ヶ所がプロコフィエフと紛らわしい』という理由で、彼はそれを破棄してし
まった。彼は西欧の点描主義を奉じる作曲家の最初の人であった。だが、彼は実際の作曲よりも彼の
音楽から他の作曲家からの影響をとり除くのに多くの時間を費やす。今夕の公演で演奏される6分間
のピアノ曲を完成するのに、フルに4年間かかったということを信じる人は、その間の事情を理解で
きると思う。そういう次第だから、奇妙なことだが、今夜の演奏が初演であるばかりでなく、また最
後の演奏ともなりかねまい。佐藤氏は私に、『この曲にほんとうのvitalityを持たせたいと願ってい
る』と語った。これはとてつもない曲だ。私は、他の曲でこれと似ている曲を全く知らない。様々な
作曲家がピアノの『響き』に関する新しい概念を創造している。モーツァルトの清潔なペダルのない
ピアノ曲、ブラームスの重厚なオルガン風の和声、バルトークやプロコフィエフの打楽器性等々。佐
藤氏のピアノ曲はハミング・ピアノを必要とする。彼はこれを非常に思いつきに富んだペダルの指示
でやっている」(三浦淳史訳)。このハミング・ピアノというタークイの表現は分かりにくい。私なら
ばこれを、「梵鐘のようにピアノの音が強く、弱く打ち鳴らされ、その響きの余韻がまさに消えよう
とするや、必然的な継起として次の音が打ち鳴らされる。これらの響きは、大小幾つかの梵鐘が遠く
から、また近くから重層的に鳴らされたように重なり合いながら、全体のサウンドを作る」とでも表
現してみたい。しかしどのような言語表現をするかは別にして、タークイが指摘したことは、この6
分間のピアノ曲が、モーツァルト、ブラームス、バルトークと並んで、まったく新しいピアノの様式
を生み出したということである。それでは彼の述べるシステマティックな方法について、考察してみ
よう。
始めに、若い頃からの友人である作曲家湯浅譲二の佐藤評を、紹介しよう。「作曲という仕事に
は、感性に任せて感覚的に音を選びとっていく仕方と、音の細部にいたるまでシスティマックに決定
していく仕方とがある。どんな作曲家でもこのいわば両極の間のどこかにいるわけだが、システィ
マックな方法をより好む作曲家の中で、佐藤慶次郎ほど、その方法に徹底している人を僕は他に知ら
ない。彼はシステムといういわゆる合理的な方法を、その極限まで追求して、その結果、遂には佐藤
慶次郎という人間の感性とまさに合一せしめてしまう。つまり、そこには合理と非合理、システムと
生きた人間、あるいはハードウェアとソフトウェアとの生きた対応があるというだけではなく、それ
らが一種の自己同一性にまで高められている結果があり、それが佐藤慶次郎の決して多いとは言えな
い、作品群であった」(注2)
それでは先ず、音高システムについて述べよう。ここでは「5つの短詩」の作曲以来、十分に検討さ
れてきた12音音列が使われている。ただしここでの発明は、旋律的な音程関係を並べて旋律の基礎に
なるような音列を作るという、12音音列を使用するすべての作曲家たちの方法を超えて、ちょうど伝
統的音楽に使用される音階のように、音列を音列本来の基礎素材的な役割に限定したことである。
従って、この曲の音列は譜例16のように、何の変てつもない半音階である。いま分析の便宜のため
に、半音階を構成する各音に1から12までの番号付けをしておこう。これらの半音階は、12音の音列
が3音ずつのグループに区分されて、1),4),7),10) の4つのグループに分けられる。(譜例16-1) この
半音階は、短2度づつ上に2回移調することができ、さらに2つの半音階、2),5),8),11)と3),6),9),12)
が生まれる。(譜例16-2) そして、それぞれのグループの中の3音は、出現する順序を入替えることが
可能であり、それらの中で6通りの配列が生まれる。(譜例16-3) また、1),4),7),10)4つのグループの
それぞれを入替えることも可能であるから、結果としてこの音列からは、6×6×6×6×3の3888通
りの配列が生まれることになる。佐藤は、この3音の出現順序を入替えることを、白血球の核の分葉
から示唆を受けたこと、そしてさらに1+1+1音、1+2音、3音の3通りのあり様を考えたこと
を、1990年の私の作曲の会「第6回アルビレオ音楽展」において「ピアノのためのカリグラフィー」
を再演することになったとき、私に明かして呉れた。それらは例えば、次の様にである。(譜例17) ま
た、この3888通りの配列は、すべてがそのまま使用されるのではなく、彼の定めた条件のもとに使わ
れる。残念ながら、この「ピアノのためのカリグラフィー」の個々の音がどのように決定されたか、
詳細はよく分からない。それでも分かるところまでは、分析してみよう。冒頭[1]のセクションを見て
ほしい。(譜例15) [1]のセクションは、1)グループに所属する音ハ(C)-嬰ハ(Cis)-ニ(D)の3音の和音
によって始まる。しかし9個の8分休符を挟んで次に始められる音は、変ト(Ges)-へ(F)+ト(G)、ロ
(H)+ハ(C)+変ニ(Des)、ニ(D)-変ホ(Es)-ホ(E)、イ(A)+変ロ(B)+嬰ト(Gis)の順序で現れる。これらの音
はすぐに、6),12),3),9)に所属する音列音であることが分かるだろう。つまり、始まりのハ(C)-嬰ハ
(Cis)-ニ(D)の和音が所属するオリジナルの音列は、1)グループが現れたのみで、4),7),10)のグループ
は省略されているのである。このように全曲が3つの音列音から構築されている様子を、譜例15で
(6),(12).(3),(9)のように示してある。
次は、リズムについてである。佐藤は作曲の方法において、1950年代にウェーベルンによって示唆
され、ドイツのシュトックハウゼンなどが試みていたトータルセリエリズムという方法と同じ方向を
目指していたことが、彼のノートから窺うことができる。このトータルセリエリズムは、音高のみな
らず、アタック(音の入り)、音の持続(音価)、強弱、音色などの音楽構成要因の全てを、1つのシステ
ムに組み込もうとするものである。しかし佐藤の場合、それはあくまでも彼独自の思想的アプローチ
から、解を見つけようと努めた結果である。1958年6月14日の日付けのある頁に、次の記述が残され
ている。「音が運動するという観念を徹底的に排除すること。音はいつでも人間の時間のある瞬間に
対応している。すなわち音はそれが出現する時、いつでも絶対的現在に置かれている。音楽における
表現は、音の連続の結果と見るべきではなく、各瞬間ごとになさるべきである。言い換えれば、音の
効果は、各瞬間において決定さるべきものである。このような音楽に認められる時間は、聴衆各人の
内的時間である。そこでこの音楽に与えられる時間の決定は、聴衆によって決定される」。ところで
私たちの日常に起きる出来事も、似たような出来事であっても一つとして同じものはない。佐藤は恐
らく愛読していた鈴木大拙の著作からの示唆であったろうか、この事実に着目して、繰り返しや、反
復が絶対に生じないように、すべて異なる動機、もしくは音型で音楽的な出来事のまとまりを作り、
それを時間の流れの上に置いて行ったのである。
また、1957年9月9日付けやその他のノートの中に、何頁にもわたる数字の配列表がある。そこで
はアタックと音価、また強弱の基本的な順序列を作って数字化し、それらの組み合わせを徹底的に考
察している。ただしこれらの配列表は、部分的にはこの「ピアノのためのカリグラフィー」のために
使われているようであるが、全てがこの曲のためのものではなさそうである。実際には実現しなかっ
た曲「Poem for orchestra」や、「Poesie sonore pour quatre a corde」などのさまざまな編成と
曲名が、これらの配列表とともに記されているからである。私が芸術大学の学生であった時は、ちょ
うど佐藤がこの「カリグラフィー」を作曲していた時期と重なっている。その時期のある日彼を訪ね
てみると、横長に裁断され、楽譜の断片が書き込まれた小さな5線紙が、机の上に山と積まれてい
た。この断片はいま考えてみると、「カリグラフィー」の形式を構築するための、重要な手段であっ
たのだと思う。しかし残念ながらこの断片は、遺品の中に見つけることができなかった。そこでここ
では彼のシステムを理解するために、楽譜を分析するしか方法がない。まづここでは譜例18のよう
に、13通りの音の入り方を示すアタック列が考えられている。13番目のアタックは極めて短い音価な
ので、装飾音符で表わされると考えてよい。そしてこれらのアタックは、持続が与えられて譜例19の
ように、3つの3音づつのリズム型に分析出来る。いまここでは分かり易いように、余韻は原則とし
て省略して置こう。この譜例19を参照しながら譜例15を見るならば、「カリグラフィー」の音楽的出
来事が、どのように組み立てられているかが理解できる。ここでは試みに、[1]から[6]までの6つの
セクションを分析したが、この方法は全曲に一貫しており、非常に統一感のある印象を与えている。
これらのリズム型の特徴は、1)3音からなる和音は、譜例18のアタック列からアタックが与えられ
る。2)2音の和音と1音からなるリズム型には、a系列 前の音価の長いもの b系列 2つの音価が
均等、もしくはほぼ均等なもの の2つがある。3)3つの単音が連続するリズム型には、c 系列 3
つの連続する音の真ん中の音が長いもの d 系列 連続する3音が均等、もしくはほぼ均等なもの
e 系列 3つの連続する音の1番前の音が長いもの の3つがある。これらすべて異なるリズム型の
アタック、音価、及び音強、音域の決定が、どのようになされたかは不明である。しかし、それらは
音高と同じように、順序を与えられ数字化されて方陣に組まれ、方陣からの選択の方法を指定される
とともに、最終的には、彼の感性に従いながら決定されたのだと思う。なお譜例19において、例えば
(7a)のような記述は、記されたリズム型が、譜例18アタック列の7番目のアタックを持ち、a系列の
リズム型に所属することを意味している。またさらに音価、強弱、音域設定についても順序列があ
り、法則性を見出すことができるが、煩瑣に及ぶのでここまでに止めたい。
この項の最後に、1990年の「第6回アルビレオ音楽展」によせた彼の言葉を紹介しておこう。
「『 ピアノのためのカリグラフィー』の創作意図を一言で言えば、純粋な生命力の表現ということに
なりましょうか。30年ほど前、この作品のアメリカ初演を聴いて、トマス・マートン氏は、『これは
音楽の新しいディメンションであり、Continuous Awakeningの音楽だ』と、ピアニストへの手紙に
記しました。絶えざる覚醒というか、持続的な覚醒というか、いずれにしても、それは私がそうあっ
て欲しいと願った、この作品の本質を言い当てた言葉でした。ピアニストが送ってくれた手紙は紛失
してしまいましたが、Continuous Awakeningという言葉は、深く脳裏に刻まれて今に至ります。ト
マス・マートン氏について、当時は何も知らなかったのですが、カトリックの指導修道士であり、詩
人、哲学者として著名な方であることを後に知りました。近年亡くなられたようですが、『空の知恵
について』という鈴木大拙氏との対談があり、また故大拙氏の回想文集で、世界に対する大拙氏の貢
献について論じておられます」。
5 ジョン・ケージ体験
1962年10月10日は、これ以後の佐藤の人生において極めて重要な日となった。彼はこの日 、初来
日したアメリカの作曲家ジョン・ケージを聴くために、十分な事前の勉強をして大阪まで出掛けて
行った。演奏会翌日に日付けられたノートに、次の記述がある。「昨日演奏会が終わった後で、友人
たちはケージを取り巻いて議論をしていた。僕は湯浅(譲二)に紹介されてケージに挨拶した。僕は
言った。『 I am deeply impressed. Thank you very much.』。実際に聴き終わって僕が持った言
葉というのは、『Just I heard!!ーまさに聴けり』だった。僕は何かしゃべりたい気持ちにはならな
かった。ーーー悟った後も坐禅を続ける事の意味がはっきり判った。それは楽しい事である筈だ。行
住坐臥、すべて坐禅という事になれば、それが最上であることは確かだ。それと同じにケージの音楽
は、その存在理由が一度判ってしまえば、もう不要に違いないと思ったが、それは誤った考えだっ
た。何度でもそれを聴くことは楽しい筈だ。しかし本当に深く達した人には、特にそれを聴く必要は
なくなるであろう。ケージは誰も聴く必要がなくなるまで、演奏行動を続けるであろうか。ー菩薩
行ー 菩薩はすべての人間が成仏するまで、その活動を続けると云われているが、彼がそうする事
は、彼にとっては極く当然の事でしかないのだ。仏の大慈大悲は、結果的にみて大慈大悲なのであっ
て、それを行う側にとっては、別に何でもないことに違いない」。
この「Just I heard!!ーまさに聴けり」と佐藤が述べている体験は、これより15年の後に、彼と同窓
の先輩慶応義塾大学医学部卒の在家の禅師岡田利次郎に出会うことによって、禅の見性の体験と同様
の体験であったと確かめられている。佐藤のこの体験というのは、「アッ!音、ぼくはどこへ去ったの
か?」と後年の佐藤が記したように、自分が音楽を聴いているという私たちの通常の意識において、
主体となる自分がなくなって、音のみがあるという体験である。しかし、佐藤にとっては禅書を読ん
だだけで師について坐禅修業をした経験を持たないために、これが禅でいう見性と同じ体験であるか
どうかの、15年に渡る長い探求の旅の始まりになったのであった。ところで禅において見性とは、何
を意味するのであろう。もちろん私のような門外漢が述べる事の出来るものでない事は、十分に承知
している。しかし生前の佐藤から「君も悟れ」と云われ、何年か私も坐禅の真似事をしてみた。そし
て結局白旗をあげた私に、それでは理論的な道筋だけは話して置こうと云われ、晩年の佐藤から毎週
のように法話を聞かされる幸運をもった私は、その道筋だけは何とか辿れそうである。
私たち見性体験を持たない一般人は、見性とか悟りとか言うだけで自分とは縁遠い人格の優れた
人、秀でた高僧などを思う。しかし、佐藤の師岡田のそのまた師筋に当たる原田祖岳(注3)は、見性
は中学1年程度(ここで述べられている学制は旧制、従って15,6歳を想定しているのであろうか)の
禅だと述べており、岡田利次郎もまた悟りの入り口であると云う(注4)。ただしこの体験は、一種の
精神的飛躍であって、必ずその瞬間に自覚できるものであり、知らない間に悟るということは絶対に
ないと云う。道元禅師の正法眼蔵に次の一節がある。「自己をはこびて万法を修証するを迷いとす、
万法すすみて自己を修証するはさとりなり」。ここで述べられている自己は、私たちがふつうに主観
的、客観的な存在であると考えている自分である。そしてこの自分が、周囲の外界を認識し、内的な
経験をすると私たちは考えている。ところが道元は世界の様々なものを、そのような自分が、見よう
として見たり、聞こうとして聞いたり、考えようとして考えているということは、迷いだと言う。そ
してそのような自分を立てないで、対象を見ようとして見ない、聞こうとして聞かない、考えようと
して考えないならば、あるがままの本当の自分と対象は一体になり、自分は対象であり、対象は自分
となって、この世界の森羅万象に働いている生命が、自ずと自分にも働いているのが分かる。これを
悟りと言うのだ、と教えているのである。しかしこのように述べられても、私たちには直ぐには分か
らない。そこで近年の医学は、私たちの意識のあり方を変える修練である座禅そのものに光を当て
て、研究する。研究の成果は、次のようである。私たちが日常活動しているときの脳では、周期の早
い波形、β波が出ているが、睡眠の初期には、これよりも遅いθ波が出る。座禅においてはこの睡眠
中と同じθ波が出て、脳の興奮を押さえている。しかし睡眠と異なるところは、自律神経中枢の働き
が高まる点にある。自律神経は私たちの意志では働かせることが出来ないのであるから、座禅によっ
て日常的な脳の働きが静まり、逆に基本的生命の働きが増大していると結論出来る。そしてこの状態
を、禅では静慮(じょうりょ)と云うのである。(注5) また創造工学の中山正和(注6)は、この悟り
を新しい創造的発見の過程として考えているが、この考え方は私たちにも分かりやすい。悟りも発見
も問題を解くという点では同じであり、発見は知的な努力がなされ尽くした大分後で、突然にハッ
と、一瞬に気づくものだからである。そしてこの発見は、理性的な予測の範囲にはなく、鋭い歓びを
伴うものだからである。従って岡田は、「悟りは禅の専売特許のものではありません。仏教以外の宗
教、諸道、諸芸に精進される方々には、時として『悟り』と同じ体験をなさった方が多数おられるよ
うです」と述べている。
中山は云う。いま自律神経の中枢を働かせるような命、そのものは分からないからXと仮定しよ
う。そうすれば後はコンピュータに類推して私たちの脳の働きを構築できる。このイノチXの働きで
私たちは、K.ローレンツが刷り込みと名づけた3歳の頃までの経験を、無意識の記憶として脳の深層
に蓄えている。これらXと刷り込みの働きによって、私たちは様々な経験をイメージとして大脳右半
球に蓄えているが、これらのイメージには、言語化されていない記憶と、言語化されていつでも論理
化できる記憶の2つがある。大脳左半球には、言語が記憶されている。言語には、自分の経験的なイ
メージとしっかり結びついたコトバもあるが、記号としてのコトバのみが記憶されていて、イメージ
のない言葉も沢山ある。そして私たちは何かの問題に直面したり、外界から刺激を受けたりすると
き、これらの記憶を引き出し、大脳前頭葉にある論理、計算脳によって思考を進め、解決し、行動す
る。さて、このように脳を規定するならば、この創造的発見の手順は次のようである。1)正見 問
題となっているものを、正しく観察すること。ここでは自分の体験したイメージと、これらに結びつ
いたコトバ(中山は真実のデータと云う)のみを観察することが大事で、他人から聞いたり、本から
得たコトバは除外する 2)正思 正しく推論すること。これがとても難しいのであるが、自分の固
定観念や偏見によって論理づけるのではなく、データそれ自体が自然に語りかけるように推論するの
である。ここで禅は、莫妄想という。私たちは正しく推論しないで、ともすれば、正しくないイメー
ジに引きずられたコトバを生みがちだからである 3)正念 コトバが消えてイメージが一人歩きす
るようになること 4)正定 正しい判断が自動的に定まること。禅ではこれを三昧、或いは、意識
即無意識のように云う。要するに中山は、悟りは私たちの創造、発見の過程と同じ過程と見ており、
対象が1つの問題に限定されるか、人生全般であるかの違いによって創造工学の領域に入るか、宗教
に入るかだと考えるのである。
それではこれをさらに、私たちが音楽を聴く場合になぞらえて考えてみよう。音楽のもつ大きな特
質は、絵画などとは異なり、刺激を人間の知的過程を通さずに、情動に直接働かせるところにある。
周知のように私たちの脳は、大脳という2つの半球からつくられている部分、それを支えるように脊
髄と繋がっている脳幹、大脳と脳幹の中間にある大脳辺縁系の3つの部分に大別される。この中で耳
という器官は、目の器官とは異なって大脳の新皮質における領域の分化が不十分であり(絵画的、文
学的連想が起こり易いということであろう)、人間の情動を生む部位の大脳辺縁系、及び脳幹へと直
接に繋がっている。そこでこのことを利用して、古来から音楽は、精神障害の治療の道具として使わ
れたのである。音楽を聴く私たちのあり方には、様々なものがある。専門的な音楽の素養を持たない
人が音楽を聴くあり方は、次のようであろう。1つは、何か他のことをしながら聴くともなしに聴
く、いわゆるBGM(背景音楽)などに耳を傾ける聞き方である。この場合には、脳の知的に働く部分
や、意志や運動に関与する部分は他の行動に向けられているのであるから、音刺激は大脳辺縁系及び
脳幹の部分にのみ伝わって、静かな音楽は精神を鎮静させ、賑やかな音楽は精神を興奮させるような
気分を生みだす。2つは細部の目立つところだけに耳を傾けたり、他のことを連想したりしながら聴
く聴き方である。この場合には脳の知的な部分と、情動の部分が共に少しずつ働いているであろう。
次のようにである。彫刻家の高田博厚は、「音楽の不思議な魅力の1つは、はじめて聴いたときの情
景が密接に音楽と結ばれており、浮かび出てくることだ。かって私は絶望のある時、パリを逃れてブ
ルターニュの海岸へ行った。荒い海際の小宿の部屋でうとうとしていると、どこかで女がブルター
ニュの子守唄を歌っている。それが私には昔、母が歌ってくれた『ねんねんころいち』に聴こえ涙ぐ
んだ。バッハのカンタータはそれと同じものを持っている。人間本質から出てくるあの普遍な深さ、
なつかしい深さに私は無条件に参る」(注7)。もう1つ、小説家五味康祐の事例。自ら運転する自動車
によって事故を起こし少年を死に至らしめた彼は、いても立ってもおれず辛うじてレコードでモー
ツァルトのレクイエムを聴くことで、騒ぎたつ心を鎮めたと云う。「茫然と、ただ事故の瞬間の光景
や、私の車に飛ばされていった少年研治君の毬のようなあの軽さや、凝視、絶望感、悔い、血、そん
なものが脳裏に甦って、かんじんの音楽は、何も聴いていなかったと云っていい。それでも、私は聴
いた。また始めから。『入祭文』のファゴットと、バセット・ホルンののびやかな旋律に始まり、バ
スから順次ソプラノに及ぶ合唱で『主よ、永遠に安息を与え給え。絶えざる光をわれらの上に照らし
給え』と唱いだすと、私のうちに或る安らいだ憶いがひろがってくる」(注8)。この2つの事例の前者
の場合において音刺激は、単純な旋律を認識する最小限の知的活動を通して大脳辺縁系の記憶脳であ
る海馬などに働いて、普段は忘れている記憶や、深層に刷り込まれた無意識の記憶を呼び覚まし、そ
れを子守唄の旋律にのせて論理化しながら、基本的生命維持を司る脳幹に直接作用して、深い感情を
生み出したのであろう。後者の場合は、音楽を聴くことに集中することによって音と一体になり、座
禅におけるような静慮を生み出すとともに、罪の意識、深い反省のような考えても仕方のないコトバ
記憶が切れて、音楽の論理とともに罪の許し、魂の救済のような解決を見い出したのであろう。
周知のように音楽は、音と音の繋がりによってイメージを呼び起こす。それは「白い遠景、淡い桃
色の花、絶望」(注9)のような詩の言葉が、イメージを呼び起こすのと同じである。しかし音楽は詩
の言葉以上に、ある音楽様式の使用規則の範囲内において、音の進行が論理的に構成されている。こ
の音の進行の論理によって作曲家は、緊張と弛緩、興奮と抑制、葛藤と解決などを構成するのである
が、この論理は、集中して聴く聞き手には自ずとある発見へと導くことになり、深い感動を生み出す
のだと思う。ちなみに脳幹には幾つもの神経核があり、この中でA10の神経核からはドーパミンとい
う、ちょうど肉体の苦痛を和らげるために使われるモルヒネにも比べられる脳内麻薬が深い感動時に
は放出されて、至高の感情が生じるのだと、脳科学はこれを裏付けている。 他方、私のように専門教
育を受けた者には、このような深い感動はほとんど訪れることがない。作曲の専門家はつねに、この
作品はどのように組み立てられているか、動機は、テクスチュアは、楽器の組み合わせはなど、或い
は演奏家ならば、テンポは、音程は、音色は、フレージングはなどなど、自分の音楽的基準に照ら
し、吟味しながら知的に聴いているからである。ここでは道元の云う「自己をはこびて万法を修証す
るを迷いとす」を、文字通り実践しているのである。ところで近年の情報理論は、音楽を次のように
考えている。ある様式の基準の範囲において、ある音楽的な出来事が起こり、聴き手はその出来事か
ら次に起こるべき音楽的な出来事を意識的、無意識的に予想する。聴き手の予想がつねに当たるなら
ば先行する出来事の情報量は少なく、音楽的な意味を生まない。反対に予想がつねに外れるならば、
先行する出来事の情報量が余りにも多く、意味はあるとしても、ほとんど出鱈目に聞こえてしまい、
聴き手は聴くことを止めてしまう。音楽の様式的な基準とは、例えば機能和声の支配する音楽におい
ては、ある和音が次にどのような和音に続いて行くかの確率体系と考えられるのであるが、この音楽
の確率体系は、歴史に沿って厳格なものから非常に緩やかなものへと発展してきた。そして今日で
は、人間の情報処理能力を超えたとさえ考えられている。音楽の意味は、ロール・シャッハ・テスト
の染みや天井板の複雑な年輪の模様から、意味を見い出すのと同じ状況になってしまったのである。
さて、佐藤のケージの音楽からの見性が発見であるとしたら、それでは佐藤は何を発見したのであ
ろうか。佐藤はノートに書いている。「『Just I heard!!』の体験は、ケージの音楽が与えたものでは
ない。ぼくが自分の力でそれを得たのでもない。たしかにそれは、起こったのだ」。「悟るために
は、芸術を放棄すべきだと道元は云っている。ぼくは見性したいと願っていたが、作曲をも放棄し
て、到達できるかどうかの当てのない見性に向かう事は、ぼくをためらわせていた。しかし今、道元
の云っている事が良く分かる。それに比してもっと大事な事など、あり得ないのだ。作曲することと
日常の他の行為とどう違うのだ。悟って、しかも音楽を書くことができる事を、ケージはぼくに教え
た。ケージは何と見事にぼくの理想だったものを、ぼくに見せてくれた事か。ぼくは今ほど自分を活
動的であると感じたことはない」。作曲すること、即仏道精進の道であったことの発見、これが佐藤
の、発見であった。それではケージの音楽は、どのようなものであろうか。ケージが1954年にヨー
ロッパの聴衆の前に初めて現れたとき、有力な批評家であるシュトゥッケンシュミットは敵意に満ち
た口調で、次のように述べた。「作品の1つは『2人のピアニストのための12分55秒677」という題
がついていて、約13分の間ずっと、小鳥が囀るようなチューチューという音と何かを打つような音が
続いた。それらの音は、爆発的なスタッカートでピアノから噴出する感じに鳴らされていた。時折
チュードアは、猫笛やおもちゃのトランペットを吹いたりする。次にハンマーでピアノの金属部分を
叩いたりする。その間ケージは我関せずの態度でピアノを弾いたままであった」( 注10) 。音楽史を通
じて作曲家の仕事は、音高、リズム、音色を操作しながら、彼の感情の論理に従って、音による建築
を構築することであった。そしてこれの到達点が、トータル・セリアリズムという音楽を構成する
様々な要因、より正確にはパラメーターと云う数学用語を使うのであるが、音高、音価、アタック、
強弱、音色などをすべて音列化して、それらの現れを作曲家の知的な支配のもとに置こうとする音楽
の出現である。しかしこの試みは、音価の順序列において序列の1番目と2番目の差、11番目と12番
目の差を等価のものと私たちの耳が聞き分けられないことによって、また、強弱の順序を与えられた
音列の各音が同時に鳴らされる場合に、強い音が弱い音を覆い隠してしまうことによって、知的操作
の限界を自然の音響現象によって教えられることになった。そこでケージの試みたことは、このよう
な音のパラメーターを知的に操作するという、人間の考え方そのものを放棄することであった。ケー
ジは云う。「音楽において習慣化しているものに、音階、旋法、対位法、和声理論、音色の研究があ
る。しかしこれらは、数の限られた離散的な音発生のメカニズムと関連して行われている。ところが
磁気テープは、音楽的実在が、音空間全域のどの地点でも線や曲線など、どのようなものに沿っても
起こり得ることを明らかにした。(ここでの)音楽を書く目的は何だろうか。意図的な無目的性、或
いは無目的な活動、これらの活動は生を肯定する。混沌から秩序を生み出したり、創造の向上を目指
す試みではなく、ただ私たちが生きている生そのものに目覚める方法なのだ」( 注11) 。そしてこのよ
うな方向を取るようになった事について、「鈴木大拙博士の講演に出席し、文献を読むことによって
禅に関わらなかったら、自分がこうした行動をとったかどうか疑わしいとは思うが、私のすることを
禅のせいにしないでもらいたい」とも云うのである。
ケージの演奏会の3日後の10月13日、佐藤はノートに見性、或いは発見の過程を次のように書いて
いる。「『Aria and solo for piano with fontana mix』を聴いたとき、いつ『それ』がぼくに起
こったか云う事は出来ない。ぼくは『おやっ!』と思ったことを憶えている。その夜、ぼくはケージ
の音楽を素直に聴いて、ぼくがどんな反応を示すか確かめたいと思っていた。『おやっ!』と思った
時 、 ぼくは音と 1 つになったように感じた 。 ぼくの内部の何かが 、 ぱっと働いたように感じ
た。sound- - -subject- - - object- - - と云う言葉がひとりでにぼくの脳裏を過った。音楽が終わった
時、"just I heard!!"と云うつぶやきが、ぼくの口からひとりでに漏れた」「John Cageよ、ぼくがあ
なたの音楽を聴き、『それ』がぼくに起こるまでは、ぼくはあなたを信ずることが出来なかった。沈
黙の音楽の事を聞いたときも、happening eventと云うあなたの催しも、それらは悟りを得た禅匠の
みがなし得る事でしかないと思っていた。あなたがそのようなやり方を、禅の知的理解からアイデア
として得ただけで、悟りを得ていないなら、あなたの行為のすべては『でたらめ』と云う事になる。
またもし、あなたが悟りを得ていたとして、そのような行為があなた自身にとっては正当かも知れな
いが、それを音楽と呼ぶべきかどうかは疑問だった。しかし『それ』がぼくに起こった今では、すべ
てがはっきりした。人々がそれによって(ただ)「聴く」(ただ)「見る」になるような機会を提供
すること。それより素晴らしいことがこの世にあるだろうか」。このように書いた佐藤は、4日後の
17日、再びケージを聴きに大阪へ行った。次の記述がある。「ぼくはケージの音楽を聴いた。予想し
得なかったことが起こった。第1曲目『Aria and solo for piano』を聴いた時、第1音が始まるやい
なや、ぼくはもう音楽を聴く喜こび、美しい音のさ中にいたのだ。何と快よい音楽だろうか。ぼくは
音と一致しようとか、集中してより良く聴こうとする事なしで、(恐らくそれ故に)美の眞只中にい
たのだ。ーーーそして驚いたことには、つい1週間ほど前のぼくには耐えられないであろう騒音の音
楽が、ぼくには全く美しいのだ。10日の演奏会のときには、時間の長さによる退屈は感じなかったと
は言え、特に美しいと呼ぶべきものではなかった。ところが今度は、すべてが全く美しいのだ。演奏
会の後でケージに会って、ぼくに起こったことについて話した。ぼくはケージに禅的な意味で『そ
れ』を起こさせる事を意図しなかったかと訊ねた。答えは『No!』であった。(とするならば)こと
によると、別のmomen tによっても、ぼくはそれを悟ったかも知れないのだ。しかし何はともあれ実
際に、ぼくはケージの音楽において悟ったのだ」。私はこのケージの『No!』こそが、以後の佐藤の
進むべき芸術の道を方向づけたと思う。何故か。仏教では求道の方法を声聞、縁覚、菩薩に分類す
る。悟りを中山の定義のように問題解決のための発見とするならば、発見は声聞縁覚道のみの精進で
出来る。声聞縁覚道を仏教では小乗というが、これは自分の問題のみを解決する道である。しかしも
し自分だけではなく、他人をもこの道に気づかせたいと願うならば(菩薩道と云う)、自分と他人が
1つにならなければならない。音楽が組織化されてある表現を持つ場合には、聴き手は当然のことな
がら知的に予想を立て、論理的な意味を見出そうとする。そこでケージは紙に明けられた穴を通して
記号を書き入れたり、コイン投げによって配列を決定するなど、さまざまな手段によって後続する音
を予見出来ないようにする方法で、音をそれ自体のままに放り出し、意味を聴き手に見出せないよう
にする。そうすればケージが佐藤に語ったように、ケージの体験した「音に耳が開かれる」状況が聴
き手に訪れると、ケージが信じているからだ。しかし聴き手がケージを信じることが出来ないなら
ば、或いはまた「音に耳が開かれる」ことを信じることが出来ないとするならば、ケージの音楽のあ
り方は伝統的な音楽から見れば出鱈目なのであるから、1度でケージを聴くのが嫌になる。そこで佐
藤は16日づけのノートにおいて「ケージよ、もし聴衆があなたを信じ、あなたの音楽が聴衆を感動さ
せるものなのだ、と信じないとき、聴衆は永遠にあなたの音楽を楽しむには至らないだろう。それで
も良いのか」と書いたのであった。しかしそれは、ケージに問うたと云うより以上に、佐藤自身に対
する問いであった筈である。佐藤が、もし「それ」を他の人々に知らせる方法としての芸術行為であ
るならば、人々がもっと「それ」に気づき易い芸術行為のあり様があるのではないかと疑問を抱いた
ことは、ここで仏教用語を使うならば佐藤が、菩薩道における慈悲心にはっきりと目覚めたというこ
とであったと思う。そしてこのケージの音楽への疑念が、耳というより発達していない、そして情を
生み易い感覚器による音楽分野から、より発達した眼という感覚器を使う美術の分野へと、佐藤が
徐々に創作の関心を移行させた所以であると、私は理解するのである。武満徹は、佐藤が1974年に南
画廊において美術の分野での最初の個展を開いたとき、「佐藤が、音楽に求めた純粋性は、結局、詩
とか音楽とか、一見純化された様式を通しては実現されないものであることが、いまになれば、私は
自分のことのように理解できるのである。ジョン・ケージの思想に佐藤が影響されたことは疑えない
が、ケージの場合より佐藤のほうが真摯である、とも云える。いや、いっそう切実であったと言い換
えたほうがいい。ケージは、否応もなくその背後には手応えのある城塞を背負うものであり、そこで
は、勇気の揮いようもあった。が、私たちが目覚めたときには、何ものもなく、この人生そのものを
問うより仕方ない」と述べた。この「ケージの思想に影響された云々」には、武満がケージに出会う
以前の佐藤の禅研究の深さを知ることが出来なかったのだから、そう見えたことと云わざるを得ない
が、「結局、音の世界すらも、彼にとっては限りなく開いてゆかねばならぬ実験フィールドの1つ
だったのである」と述べた山口勝弘( 注12) や、「今度発表する作品は、いわゆる音楽ではなくとも、
その発想の根にあって、1つなのではないだろうか。その根から出た花は、根にとらわれずに自由に
咲くだろうが、佐藤の指向性とこの世界との接点である作品、(それは)物心一如の花として存在す
るにちがいない。この花は、万人が愛でるべき花なのだ」と述べた湯浅譲二(注13)とともに、私は、
優れた良き理解者たちに取り囲まれていた佐藤の幸福を喜ぶのである。
6「10の弦楽器のためのカリグラフィー 第2番」
「ピアノのためのカリグラフィー」を1960年に書いた後、佐藤は1962年に「9本の弦楽器のための
カリグラフィー」を、そして1964年には「10の弦楽器のためのカリグラフィー」を作曲した。自筆譜
を見ると、「9本の弦楽器のためのカリグラフィー」はA,B,Cの3つの楽章からなり、A,B,それぞれ
の楽章はA,B,A,Bの順で繰り返して演奏されるので、全体の楽曲としては、A,B,A,B,Cの5楽章で構
成されている。ただしA,B,2つの楽章は、1回目は弱音器を着けて(con sordino)演奏され、2回目
は弱音器を外して(senza sordino)演奏されることによって、変化が付けられている。音列は「ピアノ
のためのカリグラフィー」と同じ短2度堆積の3音のグループから成るが、1つの楽器による3音の
旋律、2音の旋律、或いは異なる楽器間の受け渡しによる旋律が作られ、全体として表現的な印象を
与えている。しかし「10の弦楽器のためのカリグラフィー」になると、旋律的な表現は一切影をひそ
め、楽器群がただ1つの合音を奏するだけになる。この作品に続く「10の弦楽器のためのカリグラ
フィー第2番」は、1965年11月30日、当時日本を代表する現代音楽の団体として活躍していた、20
世紀音楽研究所の主催する第6回現代音楽祭での招待作品として初演され、佐藤のアコースティック
な楽器を使っての最後の作品となった。これ以後、佐藤は決してアコースティックな楽器のための作
品を書くことがなかった。この音楽祭は、著名な音楽批評家の吉田秀和を筆頭にして、入野義朗、柴
田南雄、黛敏郎、諸井誠など、当時の日本を代表する現代音楽作曲家7人によって構成される研究所
メンバーによって運営されていた。そして1957年にその第1回を軽井沢で開催して以来、日本の現代
音楽の流れをリードしてきた。この第6回においては I.クセナキス、P.ブーレーズ、W.ルトスアウス
キー、K.ペンデレッキ、G,リゲティという音楽史にその名を止めることになった外国の作曲家ととも
に、日本人作曲家の作品が演奏されたのである。佐藤は音楽祭のプログラムに、自分の作品について
次のように書いた。「昨年ニュー・ディレクション(演奏家団体)のために書かれた第1番の場合、エ
スプレッションが避けられたというならば、ここでは、それは抑えられていると云えましょうか。い
ずれにしても、受動的注意の契機を出来るだけ排除して、聴き手の主体的注意の場とすることに努め
ました。すなわち、ここで意図されているのは、聴くという行為それ自体が人にもたらすものと相
まって、ひとつの音楽的世界を成りたたしめるような作品です。これが良き享受にあたいするもので
あることを願っています」。要するに佐藤の意図は、受け身の聴き手の知的過程や情動の過程に訴え
るのではなく、主体的かつ無心の聴き手に対して、音楽自体の持つあり方によって、「それ」の存在
に気づかせるような作品の提示ということであった。しかし、佐藤は自分の作品の提示や説明に際し
ては、決して「それ」や悟り、或いは見性などという言葉を使用しなかったし、むしろそれらを示唆
するようなことも、積極的に避けたことに注意して頂きたい。禅では「莫図作佛」と云うが、悟り体
験を前提にしての座禅は、待悟禅と云って排斥される。同じように発見の道においても、考えに考え
抜いて、発見などを諦め、それを忘れたときにこそ、始めて発見が起きる。佐藤がこのことを意識し
ていない筈はなく、従って佐藤としてはただ、聴いて下さいと云うだけの意味で、解説を書いたのだ
と思う。それでは具体的に、作品の内容に立ち入ってみよう。
全体で151小節の長さを持つこの作品は、ときに4分の2拍子が混じるが、ほぼ一貫して4分の3
拍子で書かれている。またテンポについては、ピアノのためのカリグラフィーのようなテンポ変化も
なく、4分音符1拍が、ほぼメトロノームテンポ42に指定されている。私がこのテンポ指定に従って
コンピュータで曲を制作した結果では、曲の長さは10分35秒であったが、初演の岩城宏之指揮N響メ
ンバーの演奏録音では、14分30秒ある。佐藤のこの曲は、知的に音楽の論理を見出そうとすることは
勿論のこと、情において何かを感じようとすることも、連想的なイメージを追いながら聴くことも一
切放念して、ただ聴く、或いは、佐藤の師の岡田の表現を使えば、聴けば聴きっぱなしのように聴く
ことが要求される。そのために佐藤は、曲中に繰り返しや、表現として目立つ箇所や、その他、次の
音楽的出来事を予想させる契機となる箇所を徹底的に排除するために、曲における出来事の非予想
性、不確定性を計量し尽くした。そのために彼の音楽は記譜された通りに演奏されることが絶対条件
となるが、残念ながらこの初演の録音は、楽譜の指定通りには演奏されていない。メトロノームテン
ポも30に近い、余りにも遅すぎ、情念を込めた演奏になっている。ケージの場合であれば、彼の非予
想性、不確定性は即興的な演奏に委ねられる。そのためたとえ偶然ではあるにしても、部分としては
予測の立つ部分が生まれることにもなる。しかしこの曲の佐藤の場合においては、全体的な統一は保
ちながらも、音高群、音域、アタック、音価と間合い、強弱、奏法の組み合わせを十分に考慮し、同
じパターンが絶対に出現しないよう配慮しながら、徹底して非予想的であるべく確定されている。
従って演奏に際しては、絶対に楽譜の指定通りに為されるべきである。しかし聴取者である私たち
は、雲のゆっくりした流れを眺めたり、野の花を愛でるように、或いは、竹林の風のざわめきや小鳥
の声に耳を傾けるように、注意を逸らさずにただ聴けば、それで良いのだと思う。
それでは音高、リズムの面についてのみ、非予想性を生み出す彼の仕掛けを見てみよう。まず音高
のシステムは、譜例20のように、2つの短2度堆積の3音からなるグループが、123/678/
11121/456/91011/234のように並べられて、音列が作られている。この音列は、元来12
の異なる音しかない半音階において、18の音によって音列が構成されているために、グループどうし
を共通音で結ぶことができる。恐らく佐藤は、グループ間の進行がスムーズになることを、意図した
のだと思う。またこの音列はただ1つしか移調することが出来ず( 譜例21) 、両端のグループは、2つ
の音が共通音であることに特徴がある。そして元音列と増4度高く移調した3音から成る12のグルー
プは、(いまこれらのグループを(1),(6),(11),(4),(9),(2),(7),(12),(5),(10),(3),(8)のように、グループ冒
頭の音番号を採って番号化して置こう)A( 1) . ( 6) . ( 11) . ( 4) . ( 9) と、B( 2) , ( 7) , ( 12) , ( 5) 及びC( 10) , ( 3) , ( 8) の
3つのグループに群化されている。それでは楽譜を見てみよう。(譜例22) 一見して分かるように、3
音によるグループはすべて合音として扱われ、これらの合音には同一のアタックと持続が与えられて
いる。ただし、同時に鳴らされる、あるいは前後に近接する他のグループ音がある場合には、共通す
る音が省略されて、2つ、もしくは1つの音のみが奏される。もちろん同一であるべき持続も、次に
継起するグループ音の状況によって、異なることも生じる。また音の入り( アタック) は、譜例23のよ
うな12のアタック列から選ばれたアタックが、各グループに割り当てられている。そしてこのアタッ
クを与えられた音群にさまざまな持続( 音価) が与えられ、それらの音群が絡み合いながら音楽を構成
している。持続には、短い持続と長い持続がある。短い持続音は、32分音符単位のもの及び6分割単
位のものの2種類があり、それぞれに1拍以内の短い持続が与えられている。また長い持続音は、基
本的には4分音符が単位となっており、これらに32分音符を単位とする持続が付加される場合もあ
る。またさらにここで特筆すべきものは、それぞれの音楽的なまとまりどうしの間には休止が挟まれ
て、持続と同等の価値をもつ沈黙が、十分に考慮されて作曲されていることである。
7 音楽領域の拡大
音楽を聴くことによって静慮(じょうりょ)をもたらし、聴く人にあるがままの本来の自分に気付
かせたいという、菩薩道としての音楽の目的からすれば、佐藤がアコースティックな音楽の創作から
領域を広げて、サウンド・ディスプレイのような新しい領域へと進んだのは、きわめて当然な選択で
あった。ここでは演奏会にわざわざ出掛けることもなく、そのまま音楽に接することができるからで
ある。1965年の始め頃からの佐藤は、長さの異なる鋼(はがね)の棒を組み合わせて溶接したもの、
湾曲した鋼の棒に、鋼の螺旋ワイヤーを溶接したもの、薄く幅広い鋼板を組み合わせたものなど
(図)を、打楽器のように叩いて演奏した音をマイクロフォンでテープレコーダーに録音し、フィル
ターによる音色変化、リング変調器による鐘のような音の合成、或いはテープ速度の変更による音高
の変化など、フランスのピエール・シェフェールが1940年代後半に創始したミュージック・コンク
レートの方法を使いながら、佐藤独自のテープ音楽「スティール・リボンによるカリグラフィー」な
どを創作した。そして、それらの音楽を創作するための実験の過程で、1967年に指の接触面の変化に
よって音階を発生させる機器、「エレクトロニック・ラーガ」を創作した。これについて佐藤は谷川
俊太郎との対話( 注14) の中で、次のように述べている。「自分で作った発信器(ちょっと特殊なブ
ロッキング発振ですけど)をいじっていたら、ピョロピョロっていったんです。(そこで)回路を変
更したり、素子を変えながらいろいろいじくりまわすと、ティララッと3音くらい段階的な音が出た
んです。アレッと思ってあっちこっちやってみるけど分からない。そのうちにハッ!と気が付いたん
です。帰還回路に手が入ってたわけなんです。それから、ああでもないこうでもないと回路をいじく
り続けましてね、少しずつ音域を拡大していったんです。エレクトロニクスの知識は、小学生向きの
ラジオ雑誌を本屋で立ち読みする程度のものだから、試行錯誤もいいとこなんです。音域を可能な限
り拡大しようとして、朝から晩まで長いことやってましたね。何人かの技術者にも相談したんですけ
ど、アドバイスは得られませんでしたね。家内には、そんなことしていてどうするんだと言われます
しね。音楽好きのあるピグミー、自分にしか聞こえない音しか出ない楽器で、朝から晩までエンジョ
イしながら演奏し続けたピグミーと同じだなあ、と思いながらやっていましたよ」。
この佐藤の言葉には、創造ということへの多くの示唆が含まれている。恐らく事の始めは、佐藤は
音を出す音源としての装置を、マニュアル通りに作っていたのだと思う。すると「ピョロピョロ」っ
と、発振する現象が生じることに気が付いた。そこでこれは何か、という疑問が生まれた。そこでさ
らに試行を重ねると、「ティララッと3音くらい段階的な音が出る」第2の発見が導かれた。ここで
佐藤は最初の目的、マニュアルに従って「音源としての装置を作る」から、「ティララッと3音くら
い段階的な音が出る」発見をもとに再出発して、さらに「可能な限り音域を拡大する」現象の発見へ
と、目的を変更した。そしてこのように目的を変更した段階で、佐藤の有為の行為は、まったく無為
の行為に変化している。そこで「そんなことしていてどうするんだ」と云う夫人の発言が生まれるの
であるが、こうなれば逆に、遊びに熱中する子供と同じで、満足するまで、或いは結論に達するまで
は、止めるわけにはいかないだろう。そして自然倍音の音程関係を逆行させたような音程を発する装
置を創作して、佐藤の一連の行為は終了した。ここにはまさしく孔子の「之れを知る者は之を好む者
に如かず、之を好む者は之を楽しむ者に如かず」を地で行ったような行為の過程を、私たちは目の当
たりにするのである。ちなみに吉川幸次郎の注釈には、「楽しむとは、対象が自己と一体となり、自
己と完全に融合することである」と書かれている( 注15) 。岡潔( 注16) は私たちの理解と云う行為を、
知解、情解、信解(しんげ)の3つに区分した。ここで知解は言葉によって知ること、情解は特別な
感情を抱くこと、信解は対象と一体となり、発見に至ることと解すれば、信解はまさしく、悟り以外
の何ものでもない。そこで私たちは、道元の「万法すすみて自己を修証する」も、中山の「発見」
も、岡の「信解」も、みんな同様な人間のあり方なのだと気付くのである。そしてこれが佐藤の
「ラーガの音階は、ぼくが設定したわけじゃない。『エレクトロニック・ラーガ』は楽器であると
も、玩具であるともしないで、『何か』として人の前に投げ出した」と云う谷川への発言に繋がって
いく。私たちが佐藤の音楽の沈黙のあり様に気付くことによって、ただ聴くという態度を学ぶこと、
『エレクトロニック・ラーガ』に触れて、そのか細き音階に聴き入り、音と一体になって楽しむこ
と、「すすき」の白い球体の運動にただ見入りながら、心を静め、いのちXの働きに気付くこと、こ
れが佐藤のすべての創作に通低する主題であると、私は考えるのである。「エレクトロニック・ラー
ガ」のもう1つの特徴は、人間の身体の電導性を利用して、何人かの人が手を繋ぎ合うことによって
も、演奏出来ることである。ここには作品を通して、人々の連帯意識やコミュニケーションを強化し
たいという佐藤の願いが込められており、彼の菩薩道の現われと考えられる。1967年10月の銀座松屋
で発表されたカタログに、彼は次のように記した。「およそ音楽という名のものが、すべて火の消え
たように眠りについてしまったころ、ふと自分の指先から糸を紡ぐように繰り出してくる音、という
ものを想像してみる。大きくいえば宇宙のどこか、あるいは身辺のどこかからやってくる音を、自分
のからだが霊媒のようになって捕えるのだ、といってもよい。楽器の演奏というよりも、これは名づ
けようのない体験なのだが、もし望むならば、あなたは隣人をも{それが愛する人であればなおすばら
しい} 一体として「演奏」することができる」。この佐藤の解説に加えてカタログには、滝口修造が
「ーー人類にとって音楽の驚きは、火の驚きに先んじていたというのはほんとうかも知れぬ。ーーこ
のエレクトロニック・ラーガも古代人にとっては正真正銘のマジックであろう。しかし実際は、いそ
がしい信号の隙間からひょっこり訪れた音の珍客なのである。名づけるともなく、T h i s ma n
music !」と賛が付けられている。
サウンド・ディスプレイという用語は、一般には人が近づいたり、画面やボタンに触れることで、
音楽やナレーションなどが流れる広告、宣伝の展示のあり方を示している。そしてこれの制作には当
然のことながら、多くの人が関わり分業する。しかし佐藤はこの述語によって、作品の提示のあり方
を意味したに過ぎないので、ここでは音源の採集及び制作、作曲、発音システムの設計及び製作の全
ての過程、ちょうどアコースティック音楽の場合ならば、楽器の製作、作曲、演奏に相当するすべて
の音楽の過程を、彼がたった一人で為すのである。ここでの音源は、楽器の音はもちろんのこと、先
のスティール・リボンのように新しく創作された楽器や、さまざまな騒音、機械音や自動車の音やサ
イレンの音など、また波の音や、木々のざわめきや風の音、さらには小鳥や動物の声など、人間の聴
覚が捉えるすべての音が、音源となる。この音源を素材として、これらを変形、構成することがここ
での作曲である。そして最後にそれらはテープに録音されて、再生される。この再生の段階はアコー
スティック音楽の演奏に当たるために、佐藤は、スピーカーの数や空間的な位置の設定、さらには音
源の空間的な移動、音色的な周波数の帯域効果の設定、音の奥行き効果設定のための残響の増減な
ど、あらゆる配慮を試みている。そしてこれらの考察、実験の結果が、1970年の大阪万国博覧会三井
グループ館での、音響デザインの仕事に結実したのであった。
ところで音楽の時間というものは、音楽的出来事の短期の記憶と、それに基づく次の出来事への期
待という私たちの知的な脳の働きによって、音楽的な出来ごとが継起しながら時間を紡いで行く、と
考えるのが伝統的な音楽のあり方であった。しかし佐藤の考える音楽の時間は、時間という流れの上
に沈黙を挟みながら、短い音楽的出来事を置いて行くことによって作られる。そしてそれらの出来ご
とは、決して継起的な関連を持たない。このことは要するに、一切の出来ごとは刹那(瞬間)に生滅
するという仏教が考える時間、或いは、私たちが実感する主体的な時間を、佐藤が時間の流れという
仮定された枠組みの中で具現化しようとしたのだと考えられる。この時間というものは私たちには非
常に分かり難いのであるが、道元の説明は次のものである。「たきぎははいとなる、さらにかへりて
たきぎとなるべきにあらず。しかあるを灰はのち薪はさきと見取すべからず。しるべし、薪は薪の法
位に住して、さきありのちあり、前後ありといへども、前後際断せり」。これについての先の中山の
説明は、分かり易い。すなわち私というものの世界は、私たちが生まれて以来この目で見、この手で
触れたすべてのイメージ記憶である。このイメージの中に論理や計算で作り上げた間違ったデータが
入っていないならば、このイメージ記憶は、自ずから自然のままにあり、法位にある。このイメージ
記憶は、私たちの大脳新皮質に平面的に記憶されているのであるから、イメージとイメージの間にあ
とさきはない。従って薪のイメージについては、薪そのものについては前後があり、灰のイメージに
ついては、灰そのものについての前後はあるけれども、薪と灰の間は際断されており、前後の関係は
ない、と云うのである。このイメージ記憶が私たちの創造性の源泉であることを考えるならば、ここ
での時間は、「走る」や「動く」のように時間を予め組み込んだイメージにしか、時間は存在しない
と考えられる。そこで時間が過去、現在、未来と直線的に連続するという私たちの認識は、一つの観
念の枠組みであると考えてよいのだと思う。
さて面倒な問題に足を踏み入れたので、もう少し軽やかな佐藤の側面を見てみよう。1964年の秋頃
からのノートには時おり、俳句、或いは発句が見られるようになった。元来、佐藤は詩から創作活動
を始めたのであるから、言語による表現に関心が無い筈はない。しかしこれらは飽くまでも私的なも
のとして、絶対に他人に見せることは無かったし、ただ見る、或いは、見ようとして見ないための佐
藤自身の禅的修練の結果を、俳句の形で言語的に意識化し、確かめようとしたのであろう。
晩秋の 樹々ら寂かに 光りおり
干し物ら 晩秋の陽光{ひ}に 輝けり
{小生が干した 二た棹の洗濯物といういわくあり}
柿もまた 吾れを見ており 盆の上
石のこころ石のすがたにきわまれり
{こころー意思と書いてこころと読ませたいところ。存在それ自体の尊厳}
病癒え小春日の街を夫{つま}と行く(和子夫人)
小春日にその名を知りぬ梅もどき{慶次郎}
万象{ものら}みなわれに親しきものとなり
窓越しの秋の
陽光{ひかり}の中に、 坐っているやつ、 立っているやつ
臥てるのもいる。我が家の物達。
8 思想の深化
佐藤の生涯における1972年45歳頃から以後の歩みは、音楽の領域からエレクトロニック・オブジェ
の領域へと創作の対象を決定的に移したこと、また1977年50歳の夏に、彼と大学の同窓で医師として
開業するかたわら、在家の禅者として活動した岡田利次郎師に巡り会ったことの2つによって、大き
く決定されている。オブジェの領域における仕事については、私は専門外であるので他の研究者の筆
に任せたいが、ここでは1977年以降の彼の思想的な背景を見てみよう。
1977年に岡田師に出会うまでの佐藤にとって、禅はあくまでも独学のものであった。しかし岡田師
との出会いは、佐藤の禅体験、及び思想を急速に深めることになり、翌78年には、禅で云う大悟徹底
の体験をすることになる。従って1977年12月からは、ノートへの思想的な記述が、非常に増加してく
る。そして特に1979年5月からは、19世紀の米国の女流詩人、エミリ・ディキンソンの詩に出会った
ことから、以後12年にもわたる研究が始められた。ディキンソンとの出会いの詩は、次のものであ
る。
How happy is the little Stone/ That rambles in the Road alone , And doesn't care about
Careers/ And Exigencies never fearsーWhose Coat of elemental Brown/A passing Universe
put on, And independent as the Sun/ Associate or glows alone, Fulfilling absolute Decree/ In
casual simplicityー(注17) この日本語訳も載せておこう。小石はなんていいんだ/道にひとりころ
がっていて/経歴も気にかけず/危機も恐れない/あの着のみ着のままの茶色の上衣は/通りすぎて
いった宇宙が着せたもの/仲間と交わり あるいはひとり輝く/太陽のように独立していて/途方も
ない無邪気さで/天命を果たしている(注18)。この詩は前節で触れた佐藤の石の句と、どこか相通
じるものがある。そしてそれが、佐藤の琴線に触れたのであろう。ディキンソンは生涯で1775編の詩
を残した。しかし生前には、わずかに10編ほどの詩を匿名で発表したのみで、生涯のほとんどをアマ
ストの家の中で過ごした。死後、ようやくその詩が世に出ることになって、今日ではアメリカの生ん
だ最高の女流詩人とまで、評価されている。ディキンソンは、わが国では英詩というジャンルから英
文学の分野で扱われているが、佐藤がディキンソンにのめり込んだのは、詩の言語表現への興味では
なく、彼女の内面における神との対話が、まさしく禅の見性、そして大悟徹底という体験的な事実と
呼応する、ということの実証研究のためであった。このために彼は、手に入る限りの文献を集
め、1864年出版のWebster'sの古辞書まで購入した。しかし、いつであったか私が佐藤の家に伺った
とき、ちょうど佐藤は「もうこれで止めた」と厖大なディキンソンのノートや資料を、箱に入れて台
所の床下にしまい込むところであった。佐藤にとってディキンソンの研究は、飽くまでも、自分の納
得のため以外の何物でもなかった。しかし私には、宗教的な観点からのディキンソン研究がほとんど
見られないわが国の英文学の状況を考えれば、将来、佐藤の研究は必ずや重要なものとなるに違いな
いと、惜しまれるのである。それでは1978年のノートから、その幾つかを概観してみよう。
12月2日午前2:45と日付けられたその1頁目から、「ボールペンを見る。ボールペンと私は未分化
の総体として把握される。二即一、一即二。これを概念の世界に移して取り扱うとき、自と他に分か
れる。非思量とは分別と無分別の交わりのレベルにおける意識である。言語的把握(思量)を伴わな
いが、分別作用は営まれるのである」のような哲学的な考察が見られる。そしてこれはさらに、
「眼ー視覚的な働きの中、耳ー聴覚的な働きの中、鼻ー嗅覚的な働きの中、舌ー味覚的な働きの中、
身ー触覚的な働きの中、意ー言語的な働きの中、これらが分かるのはすべて、非思量で分かるのだ。
言葉だけが例外なのではない」のように展開されて行く。そしてさらに続けて、「以前のように、空
に執することを良しとしてきたわけではないが、無分別の分別は、言葉を持たないことであるとし、
やはり無念に執して来たわけである。言い換えれば、有念を恐れてきたと云える。しかし、根本的な
分別作用は、無分別の分別なのであり、言葉の分別も無分別の分別{根本智}においてなされているの
であり、言葉を持つこと{有念}を恐れる必要はまったくなかったわけである」の反省も記述されてい
る。要するにここには、言葉のあり様についての何らかの発見があったことが、見られるのである。
それでは佐藤の身に何が起きたのであろう。ノートに記された岡田師に当てた手紙の下書きに、次の
ものがある。「昨年3月以来、食べられるうちは仕事を坐禅に振り替えてやって参りましたが、秋も
終わる頃には、背筋の伸びも感じられ、坐禅もそれらしくなり、坐禅の進みと平行して、澄浄も進ん
できたように感じられて参りました。『そうやっているから、そうやる』というあり方で、自分をあ
りのままの自分に還すということ。これはぴたり一枚にするのに具合のよい態度だと考えられまし
た。先生にお目にかかる以前は、まことに長い間、それと逆のことをやっていたように思われます。
行為における無念を見つめようとしていたのでした。そこでの問題はやはり、自己の分裂です。11月
頃からは静慮も進んで想念もあまりなしに日常が進行し、多分11月のある日、言葉が分かるというこ
とも、物が分かるのと同じように、ただ分かるのだということに気付きました。家内が何か語りかけ
る、それに対して何か応える。言葉という一つの音の流れ。聞くときも、話すときも、分かっていて
分からないままに、その流れと同体的に流れ、そのプロセスがスムーズに進行する。これはのどが渇
いたとも思わずにそれを知り、水を酌んで飲む。そのプロセスと全く同じことのように思われまし
た。言葉の問題をこのように理解いたしますと、言葉即有意と考えておりましたが、一切の分別が無
意識に、意識下で為されている事になります。そこで意識面には何もないという状態が持続されるよ
うになりました。そのようにしております内に、12月9日の夜、家内とともに炬燵に入っておりまし
たとき、覗くことが出来ない筈の意識下、無意識が何かポーと明るくなっておりまして、いや、無意
識が見える筈がないと思いましたが、そこに世界、即ち私の環境が映っているように見え、何か輝き
を増して眩ゆい感じがし、オヤッと思ってさらによく覗き見ようとした瞬間に、それは爆発し、その
まま現実の世界と化してしまったのでした。茶だんす、マホービン、ふすま、柱、ストーブ、天
井ーーー。それらは私の外にあって、私の内側にあり、私の内側にあってしかも外にある。内外無隔
礙という言葉が浮かんで、言葉で状況を捉えました。何ということでしょうか。そして心身脱落。一
人になろうと炬燵を出て、2階に上がりました。窓から街が、夜空が見えます。そうこうする内に、
その状態が納まりました。そして気が付きましたことは、(自我の)固まりが無くなっている事でし
た。固まりが無くなっているのが感じられて、(今まで)固まりがあったことが分かったわけでござ
いますが、無意識として意識していたものが、固まりであったわけです。(そして)このために意識
内に何もないように思い、世界を自分を含めて見ているように思っても、実際には超越的な眼が措定
されているということでしたが、有念、無念ということにこだわらないようになって来ていたつもり
が、実はこだわっていたということが分かりました。これは実に、思いがけない出来事でがざいまし
た。このように認識上の革命が起こることがあるなどと、それを経験するまでは誰にも想像出来ない
ことでございます」。
この記述は、私たちのようにこのような体験を持たない者にとっても、まさしく決定的な体験で
あったであろう、と信ずることのできる記述である。鈴木大拙は述べている。「禅の真髄と云うのは
人生及び世界に関して新たな観察点を得ようとするのである。それはどういう意味かというと、禅の
内面的生活に突入せんとするには、どうしても吾々毎日の生活を支配している考え方に対して、大い
に転回を生じなければならないのである。つまり物事を判断するのに、今までのような見方の外に、
まだ一つの見方があるということを知らなくてはならぬのである。もう一遍言えば、吾々の普通のも
のの見方では、どうしても満足出来ぬ。それではどうしても自由脱洒な生活を送るということが出来
ぬというならば、どこか外に道を開いて、それで最後の解決、徹底した満足を得るやうにしなくては
ならぬ。禅宗では新たな見地を開いて、そこから物を見渡すと、人生と云うものは今迄よりも、もっ
と生き生きした、もっと深き、もっと満足を与えるものがあると云うのである。斯の如き見方を得る
と云うことは、実際人間として行き得べき最も大なる精神的経験であらねばならぬ。これは決して容
易なことではないのである。火の洗礼を受けなくてはならぬのである。斯の如く人生、及び世界に対
して、吾々の今迄の立場を全くひっくりかえして、新たな観点を得るということを、禅では悟りとい
うのである」( 注19) 。佐藤が幼少の頃に感じた「自分の居場所ではない」という環境への違和感は、
鈴木大拙の述べる通りの道筋を通って、佐藤をここまで導いてきた。12世紀の中国で作られた禅の精
神深化の過程を示す、十牛図というものがある。ここでの牛は、本来の自分、或いは悟りの象徴であ
る。ここでは1)尋牛 2)見跡 3)見牛 4)得牛 5)牧牛 6)騎牛帰家 7)忘牛存人
8)人牛倶忘 9)返本還源 10)入塵垂手 のように示されている。いまこれらの解説は措くとし
て、佐藤がジョン・ケージの音楽体験によって3)見牛の見性体験を得、以後16年の歳月を経て6)
の騎牛帰家、大悟徹底の段階に達したと私は想像するのである。ちなみにこの騎牛帰家の図は、悟り
の牛に乗って、牧童が家に帰って来るのが描かれている。岡田師はこのとき佐藤に「悟りの滓が取れ
ましたね」と評したと、後に佐藤は私に語ってくれた。この体験の後の12月10日付けの頁には、感情
の吐露を滅多に記述しない佐藤のノートに、その頃佐藤が面倒をみていた母への記述がある。「母
よ、死ぬときは、あなた一人が死ぬのでは、あなた一人っきりがこの世から消えるのではない。ぼく
も含めて、あなたの世界の一切が、あなたとともに死ぬのだ。畏れなくてもよい。淋しがらなくても
よい」。
さて佐藤のこれ以後の仕事は、まさに為すべきことを為すという感で、機会を捉えては国内の仕事
とともに、国際的なオブジェの仕事が進められて行った。1983年、パリ市立近代美術館への出
品、1992年、セビリア万国博覧会への出品、1994年、モントリオール市立芸術科学館への出品であ
る。そしてこの領域における彼の仕事の集大成は、1999年の岐阜美術館主催「『在る』ということの
不思議 佐藤慶次郎とまどみちお展」であっただろう。この間、佐藤はこれらの仕事の合間を縫っ
て、禅体験の立場からエミリ・ディキンソンの全詩の解読をし、思想と坐禅の体験をさらに深めて
行った。1978年12月17日の日付けで、次の詩がある。「石コロガ石コロデアルヨウニ ボクガボ
クデアルコトガデキルナラ タトエナンノ役ニ立タナイトシテモ 石コロノヨウニ 光ヲ放ツ
カモシレナイ」。また1979年1月4日付けで、「吾が道は 坐禅まかせよ 風かおる」、「命と知る
時よ来れリ 若葉もゆ」の2句も記されている。この体験後の1979年、そして80年は、佐藤の仏道
修業にとって余程重要な年であったようであり、100頁に及ぶレポート用のノートが、36冊も残され
ている。これらのノートに記された内容は、端的に云えば、十牛図の騎牛帰家の段階に達した佐藤
が、さらに8番目の人牛倶忘の段階に達するための、必死の努力の記録である。これらに加えて、E.
ディキンソンの研究ノートも多数残されている。ここでこれらすべての内容を見ることはとてもでき
ないが、その幾つかを垣間見てみよう。「自己{ 即ち自己の内容} を同体的に分かっているものが自己
である。それにもかかわらず、観念上に現れる見るものを、自己と錯覚する。分かるということを、
相対的な認識しかないと、思い込んでいるのである」(79.1.26)「ぼくの現在の認識はどんなところま
で来たのか。理仏は超えたと言ってよい。もともと通りの、この身このままのぼくーー」( 4. 15)
「木々や草花、その形にしても色にしても、造化の妙と云うほかないような生命の展開。なんという
豊?さ。人は自然に触れることにおいて、人間もまた、この生命の展開においてあることを、おのず
から感得して来たに違いない。人間も、人それぞれに花である」( 4. 16) 「ぼくはディキンソンの精神
の遍歴を追いながら、ぼく自身も成長して来た。こちらが進まなければ、読み解くことはできないわ
けだ。ぼくの成長と、解読の進行は、絡み合いながら今日に到った。ディキンソンに巡り会ったこと
は、幸運であったと云える」( 12. 1) 「人間に生まれて来てよかったと感じられるようになる事が、仏
教であると岡田先生は述べておられた。誰にとっても人生が佳きものでありますように。ーーそれが
衆生無辺誓願度である」( 1980. 4. 16) 「自己とは限りなく透明な何かである。それは、一切とともに
あって、しかも見えない。実存的自己{ 生きているありのままの自分} は、相対化することができな
い。それは流れにに随って認得されているのである。人はそれを物の分かりとして、物と同体的に分
かっているのであり、事{ 行為} の分かりとして事と同体的に分かっているのである。(ここには)二
つの面があるのだ。物{有}から見る面と心{無}から見る面。有から無を見る、無から有を見る。ーー有
無相即。(それを)意識化することによって、それから開放され、それに対して主体性をとることが
出来るようになる。大悟徹底とは、それである。それは無我への出発点である」(1980.4.16)「坐はす
なはち仏行なり。坐はすなはち不為なり。これすなはち自己の正体なり。この外、別に仏法の求むべ
きなきなり」( 5. 18) 「無我を真実の自己として認めたところが、大悟徹底である。(しかし)そのよ
うに了解(大悟)したとしても、それは知的に了解したということであって、無我が身に付いている
わけではないのである。岡田先生の『ついには我が立たなくなる日がくるのです』と云われるときま
でには、充分な工夫の持続を要する筈である」( 6. 19) 「ぼくの『内外無隔礙』体験の意義は大きい。
仏教の所説は『無心』の上に成り立っているが、その体験が無ければ、その上に展開される論理は、
空論になる。その体験を前提として、論理が展開されているのだから。」(10.30)「ケージが来日した
あの年は、1962年だったか? もうあれから20年近くになる。あの『ただやってる』の体験以来、悟
りとは何か、禅とは何か、即ち「如何是祖師西来意」の問いは、ぼくにつきまとって離れなかった。
或るときは、その思いを蹴飛ばしてやりたいと思いさえした。この長年の問いかけに対して、ようや
く答えが得られたのだ。『自性本来清浄』ーーただそれだけのことである。『空牛還郷一毫無佛教』
である」(10.30)。
以上このような佐藤の自問自答は、オブジェの仕事の合間を縫って、或いは、自問自答の合間にオ
ブジェの仕事をしながらと云うべきか、さらに10年以上もの歳月に渡って続けられたが、さすがに93
年、94年の66、67歳頃のノートには、自己の体験、及び思想に対する佐藤の結論が見られるようにな
り、それとともに音楽実践への復帰の記述が現れて来る。そこで本項のまとめとして、94年10月24日
から11月4日の日付のあるノートから、さらに彼の言葉の幾つかを抜き出してみよう。「ぼくの華於
空滅(内外無隔礙)体験のところを、『人牛倶忘、返本還源』に相当すると見ることもできる。その
時、長年追いかけた悟りは消えたわけである。悟りをぼくの場合の『無為』に相当するものと見、
『迷い』を『有為』に相当するものと見るならば、その悟りは、迷いと相互規定的な現実に対する解
釈に過ぎなかったわけであり、長年の間、まったく無駄なことをやっていたと云うことになる。いず
れにしても、(あの)『一心一切法、一切法一心』体験の後なおも、『非我的主体』に対する求心は
止まなかったのである」「菩提というは大悲心{ 佛煩悩} これなり」「『捨て果てて身はなきものと思
えども、雪の降る夜は寒くこそあれ』」。ちなみに人牛倶忘は、十牛図ではただの円として表わさ
れ、何も描かれていない。ということは、主体も客体も無しと真に気付いたことの象徴である。そし
てここからさらに、主体も客体もありと、再び私たちの日常の生活に戻る入塵垂手の出発点でもあ
る。佐藤は幼少時における環境への違和感から、その落ち着き場所を求めて芸術表現によって解決を
計ろうと試みてきた。しかし十分な解決は得られない。そこで彼は、もっと端的に禅的な解決の道へ
とおのずから踏み込むことになり、遂には、古来からの心と世界の探求者たち( 佛祖) が通り、達した
とまったく同じ場所に辿り着いた。そして再び音楽の世界に戻って来たのが、「如何是」創作以降の
彼の人生であったと思う。
ひるがえってみると現在の世界は、グローバル化の名のもとに国家を超えて資本が集中され、少数
の富める者と貧困への不安にさいなまれる者との二極化が進んでいる。こういう状況の中で、ヴェト
ナム戦争の最中から、反戦と被災者救済活動に尽力し、フランスへの亡命を余儀なくされたヴェトナ
ムの禅僧ティク・ナット・ハン( 注14) の、本当の敵はアメリカではなくて、ひとりひとりの貪りや怒
りの心だと訴えてきた教えは重い。彼の教える修業法は、歩くときは歩くこと、食べているときは食
べること、運転するときは運転することに集中し、そのあり方に気付くことだけである。このような
日常の誰もが為す行為のひとつひとつが、みな無我を獲得するための修業である。従って佐藤の師の
岡田の結論、「医者をやるから医者をやるだけのことである」と同じように、佐藤の結論もまた、作
曲をするから作曲をする、オブジェを作るからオブジェを作るだった筈である。それが佐藤の1980年
代の後半からの、コンピューター・ミュージックへの回帰であったと思う。彼はこの文字通りのひと
り遊びを、90年代の中頃まで続け、その後は、ヴィヴァルディ、ラフマニノフ、メシアンの徹底的な
解読、分析へと続いて行った。佐藤は芸術のあり様について、次の言葉を残している。「いわゆる芸
術至上主義的な近代芸術は、個人的な宗教と見ることもできる。近代芸術は、宗教の衰退とともに生
じてきている。その制作を宗教的行持と見るならば、作家は、その営みを通じて、自然性に近づこう
とするのである」(94.8.24)。佐藤は自分のコンピューター・ミュージックの幾つかを、大徳寺開祖、
大灯国師の「青天白日是家山」(94.8.24)の表現と考えていた。彼はこれらの音楽が、それを聴く人々
を、そこに連れて行くことを願っていた。たしかにこの偈は、佐藤の好きだった、澄みきった青空に
ぽっかりと浮かぶ無心の白い雲をイメージさせる。しかしこれらの曲は、結局、完成させて自ら発表
するところまでは至らなかった。彼の完全主義がそうさせたとも云えるし、機会を得なかったためと
も云える。何故ならば私が発表の機会を作った2回の演奏会には、これらの中の曲を、快よく発表し
て呉れたからである。いずれにしろ彼の仕事を、彼のひとり遊びのままに失なっては、余りにももっ
たいない、というのが私の正直な気持ちである。
9 「如何是第9番」
佐藤がコンピュータ・ミュージックに回帰したのは、1987年頃である。ヤマハのデジタル・シーク
エンサーと電子ピアノを結びつけて、バッハ、モーツァルト、メシアンと云うように、興味の赴くま
まに沢山の曲を作りだした。そして有り難いことに一度も誉めてくれなかった彼が、私のピアノ曲
『飾り棚の上の時間』を「これは良くできている」と誉めた上、何とシークエンサーに面倒な打ち込
みまでして、録音を作ってくれた。そのテープには、1988年10月の日付けがある。そしてシークエン
サーの使用法が一渡り渉猟し尽くされ、その小さな機器が彼の頭と手に馴染んでくると、今度は私の
差し上げた、よりグレード・アップされたシークエンサーを使ってオリジナル作品を作り始めた。こ
れらの作品数はまた、ノートと同じように厖大なもので、私の手元に彼から送られたカセット・テー
プの録音が、78本、さまざまなヴァージョンを試みながら曲数にして160曲ほどもある。彼はこれら
の作業のために、94年3月28日のノートに「現象の観察、帰納、そして演繹。その観察すべき音の現
象を出現させるべき手段としてのコンピュータとシンセサイザーのシステム。朝から晩まで、晩から
朝までコンピュータ馬鹿。現象の観察による発見。現象を再現させることが出来るためには、方法が
はっきりしなければならない」と記している。考えてみればこの記述は、カリグラフィーやエレクト
ロニック・ラーガ、またオブジェの制作のときとまったく同じ制作態度である。佐藤は若い頃から、
作品を作るための方法と作品の内容との関係について、ずっと悩んで来た。「ピアノのためのカリグ
ラフィー」を作曲していた1959年のノートにも、「方法論を重視する人を、何か外的なもののみに惹
かれて、内的なものを閑却しているように思う人がいる。しかしある内的な欲求が、ある方法を思い
付かせるのと同時に、方法論が( 内的) 発想を触発する。それらは相互的なものである」と述べて、自
分のあり方を励ましている。しかしここではもはや、方法と内容というようなことを気にすることす
ら、まったく見られない。1992年12月22日のノートには、「末期の一句 言葉で云えば『おのずか
ら』」と記され、「生来たらば生、死来たらば死、おのずから生き、おのずから死ぬ」とも記されて
いる。この佐藤の「おのずから」こそは,先の中山の云うイノチXの働きのことであり,道元の云う
「万法すすみて自己を修証する」あり方である。要は作品の制作においては、計らうときは計らいを
尽くし、成るときはおのずから成り、そして在ると云う、中山の述べた発見のプロセスと同じこと
を、佐藤がそもそもの始めから行っていたことの、確信の言葉と考えてよい。そして、さらに言えば
佐藤は、本来的に一作一作発見、或いは、悟りを繰り返していたのだと云ってもよい。しかし彼の我
が立ち、十分な自覚に達しなかった間は、つねに余計な迷いや悩みを、頭の中に描き出して来たので
あろう。佐藤の師岡田は、ある弟子に、「仏道は修行すればするほど身につく。身につけばつくほど
まだだめだと思う。そうしてまた修業する。この繰り返しだよ」( 注20) と教えている。思えば佐藤
は、芸術に心を向けた青年期から死に至るまで、この師の教えをおのずから行じていたのだと、私に
は見えるのである。
「平成3(1991)年9月9日付けのテープに「如何是第1番」がある。この如何是と題された曲は、1992
年5月4日の「如何是第10番」の録音まで10曲ある。そしてこの頃は、やはり私の差し上げたアタリの
コンピュータを使って制作していた。1992年10月16日付けのノートに、次の記述がある。「如何是
はそのまま問処道伝の応えである。自ら呼んで『如何是』となす。そして又、自ら応えて曰く、『生
也全機現』{ 逢茶喫茶、逢飯喫飯は、生也全機現と同じこと} 。自己とは、永遠の如何是である」。佐
藤はこれらの曲で、聞き手に静慮を生み出したい、と述べている。これはまさしく菩薩道の実践以外
の何物でもあるまい。此の如何是シリーズのうち、4番は私に、そして5番は岡田師に捧げられた。
もちろん私に対する献呈は、シークエンサーやコンピュータを差し上げた返礼であったろうと、私は
理解している。ところで佐藤は、1996年6月の私の同人の会アルビレオ音楽展で、これらの作品の中
から「初夏独嘯(A random singer i n the early summer '94)ーコンピュータによる」を発表した。
このとき私はプログラムに、次のように書いた。「もう10年ほどにもなるであろうか。師の佐藤慶次
郎はヤマハのQX5に始まって、今日ではアタリのパソコンを駆使しながら厖大な作品を生み出してお
られる。しかし師は音源その他に不満足なために、決してこれを発表する意志を持たない。私たち彼
の側にいる幸運に恵まれた者は、これらの作品の一つ一つから貴重な示唆と喜びを得ているので、何
とかもう少し世に知らしめることが出来ないかと、ようやく師を説き伏せ、1992年に幕張でのコン
サートで発表して頂いた「インヴァース第4番」に引き続いて、この度、多くの作品の中からさらに
1曲を選んで世に紹介することが出来ることを、とても嬉しく感じている。この曲について、特別な
説明をする必要はないであろう。私たちが小川のせせらぎや風のそよぎに耳をそばだてるのと同じよ
うに、無心に聴き入って頂ければーーと思うのである」。
さて、これらの曲の中で佐藤が自ら発表したただ一つの曲は、2003年、岡本太郎美術館における
「風の模型ー北代省三と実験工房」展の環境音楽として使用された、「如何是第9番」である。この
曲はフルートとピアノの音色の2重奏として作られているが、フルートとピアノの音の配分の仕方の
違いにより、5つの異なる版がある。佐藤はこの曲によっても聞き手の心に、オブジェの「すすき」
などと同じような静慮をもたらすことが出来たら、と願っていた。ちなみにこの曲の音素材は、コン
ピュータのランダムな音型をもとに、作られている。そしてコンピュータの特性を生かして、1拍ご
とにテンポを変化させるとともに、フルートとピアノのテンポをずらすなど、十分な実験と観察を重
ねた新しい工夫が加えられている。要は、ここでも佐藤の制作のあり方は、生涯を通して彼の全作品
がそうであったように、「計らい尽くして、おのずから在る」であったのである。(譜例24)
note: 佐藤のノートからの引用において、(---)のように挿入された語句は、読者の便のために私が加え
たものである。また、{---}の挿入は、佐藤自身のものである。
(多摩美術大学美術館「モノミナヒカル展」カタログより 2012年11月)
|
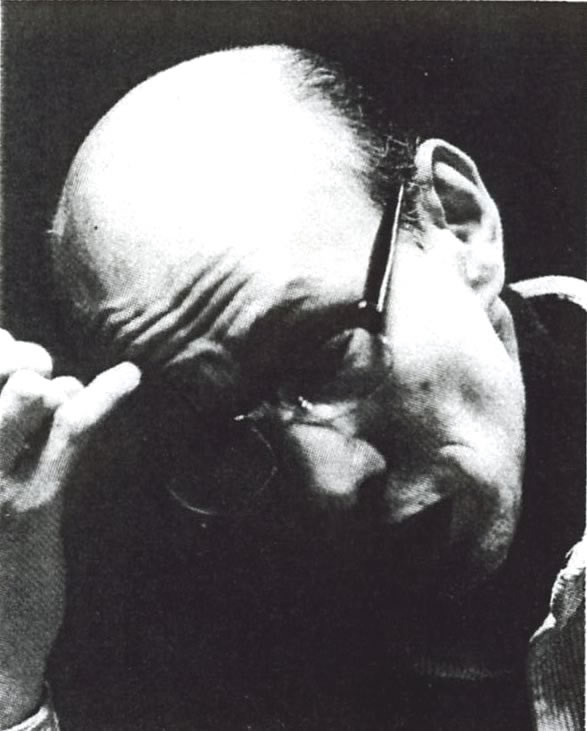 佐藤 慶次郎 Keijiro
Satoh
佐藤 慶次郎 Keijiro
Satoh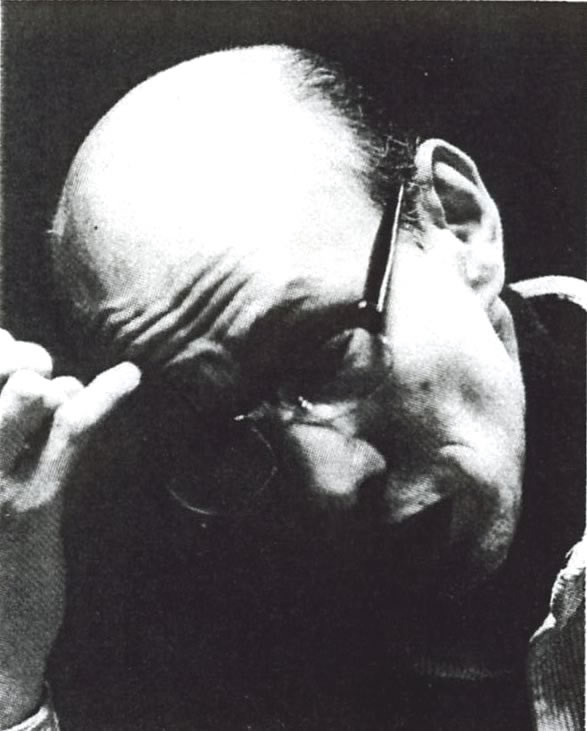 佐藤 慶次郎 Keijiro
Satoh
佐藤 慶次郎 Keijiro
Satoh