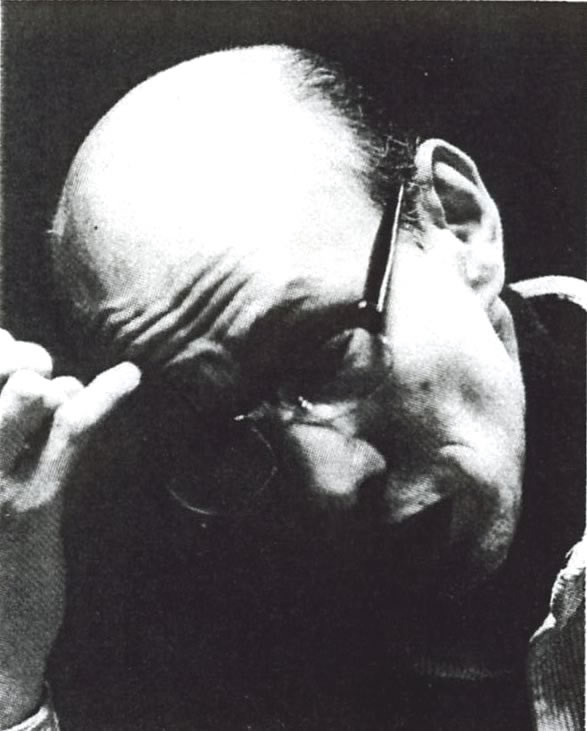 佐藤 慶次郎 Keijiro
Satoh
佐藤 慶次郎 Keijiro
Satoh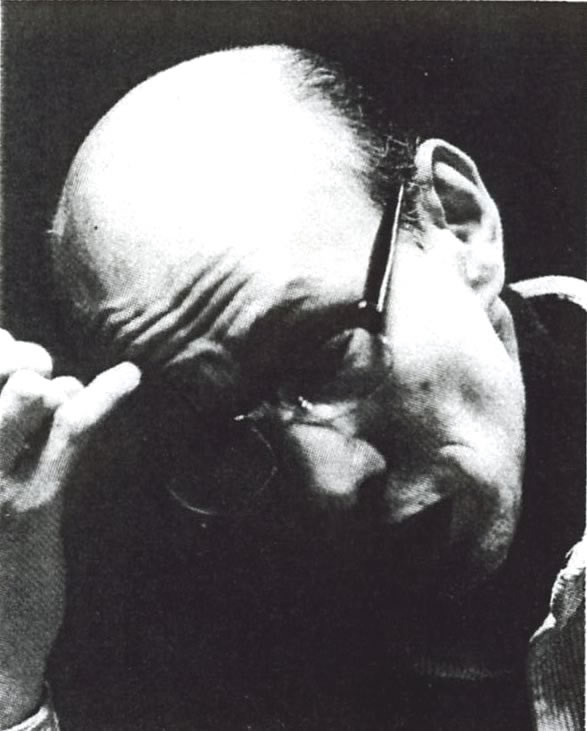 佐藤 慶次郎 Keijiro
Satoh
佐藤 慶次郎 Keijiro
Satoh| 作品サンプル 1.「ピアノのためのカリグラフィー」(1960) 曲 2.「初夏独嘯」(1994) 曲 楽譜 作品解説 「ピアノのためのカリグラフィー」(1960) -中嶋恒雄- この作品については初演以来、作曲者を含めて多くの人が語ってきた。 これら多くの解説の中で私がもっとも印象的に覚えているものは、「絶えざる覚醒の音楽」と述べたトマス・マートンの言葉である。 この覚醒とは私たちの意識をつねに目覚めさせるというほどの意味であろうが、このことから逆に私たちは、音楽を聴きながらもつねにあらぬ彼方に意識を漂わせたり、先を予想しながら自動的に聴いたり、或いは行動の伴奏として聴くような仕方で音楽を聴きがちであることを教えられるのである。 私がこのカリグラフィーを弾いた経験からすると、この曲を暗譜することは非常に難しい。 それは全体でただの12ページほどの長さであるのに、一つとして同じパターンがくり返されることはないからである。 必然的に演奏者は、曲の全てを丸ごと覚えて曲を構成する音の関係性の把握に没入しつつ演奏することを要求される。 しかしこの曲の鑑賞に際しては、聴き手は野の花を愛でるのと同じ気持ちで、聴き入って下さればそれでよいのだと思う。 それではここで、作曲家自身によって語られたもの、初演に際してアメリカの優れた音楽批評家ヒューエル・タークイが語ったもの、1990年の第6回アルビレオ音楽展で再演されたときに、その創作のプロセスについて私自身が述べたものの3点を参考に供して、解説に代えよう。 |
| 1990年11月 アルビレオ音楽展プログラム・ノートより -佐藤慶次郎- <ピアノのためのカリグラフィー>の創作意図を一言で云えば、“純粋な生命力の表現”ということになりましょうか。 30年ほど前、この作品のアメリカでの初演を聴いて、トマス・マートン氏は、「これは音楽の新しいディメンションであり、“Continuous Awakening”の音楽だ」と、ピアニストへの手紙に記しました。“絶えざる覚醒”というか、“持続的な覚醒”というか、いずれにしても、それは私がそうあって欲しいと願った、この作品の本質そのものを云い当てた言葉でした。ピアニストが送ってくれたその手紙は紛失してしまいましたが、“Continuous Awakening”というその言葉は、深く脳裏に刻まれて今に至っております。 トーマス・マートン氏について、当時はなにも知らなかったのですが、カトリックの指導修道士であり、詩人、哲学者としても著名な方であることを後に知りました。近年亡くなられたようですが、<空の知恵について>という鈴木大拙氏との対談があり、また故大拙氏の回想文集で、世界に対する大拙氏の貢献について論じておられます。 |
| 1961年1月 イタリア文化協会主催「現代音楽演奏会」初演プログラム・ノートより -ヒューエル・タークイ- さまざまな日本の作曲家たちが私に佐藤慶次郎は日本の最も才能に恵まれた作曲家だと教えてくれた。このことは、音楽会に通っている人たちが彼のことをほどんと知らないし、彼の作品もほとんど演奏されないことからみると、二重に不思議なことだ。佐藤氏はパーフェクショニストだ。彼は自分の作品を残すことがほとんど不可能になるほどひどパーフェクショニストなのだ。彼は1つの作品を書いてから2つの作品をやぶって捨ててしまう種類の作曲家だ。 佐藤氏の最初の作曲はピアノ協奏曲だった。それは毎日作曲賞を受賞しNHKから放送されたが、その後まもなく、<数カ所がプロコフィエフとまぎらわしい>という理由で、それを破棄してしまった。彼は西欧の点描主義を奉じる作曲家の最初の人であった。だが、彼は実際の作曲よりも彼の音楽から影響をとり除くのに多くの時間を費やす。今夕の公演で演奏される6分間のピアノ曲を完成するのにフルに4年間かかったということを信じる人はその間の事情を理解できると思う。そういう次第だから、奇妙なことだが、今夜の演奏が初演であるばかりでなく、また最後の演奏ともなりかねまい。 佐藤氏は私に彼はこの曲に<ほんとうのヴァイタリティ>をもたせたいと願っていると語った。これはとてつもない曲だ。私は他の曲でこれと似ている曲を全く知らない。さまざまな作曲家がピアノの‘響き’に関する新しい概念を想像している。モーツァルトの清潔なペダルのないピアノ曲、ブラームスの重厚なオルガン風の和声、バルトークやプロコフィエフの打楽器性、etc.佐藤氏のピアノ曲はハミング・ピアノを必要とする。 彼はこれを非常に思いつきに富んだペダルの指示でやっている。ある意味では、音符の実際の演奏は、ペダルが弱められるとき、次にくる音に従属する。その形式は簡素である。曲はたった1つの高いハムから始まり、少しずつ築いていって音のべちゃべちゃおしゃべりする恍惚境に至る。それから徐々に始まりの無の境地に消えてゆく。 |
1990年11月
アルビレオ音楽展プログラム・ノートより -中嶋恒雄- 「ピアノのためのカリグラフィー」、時間的にはただの6分半ほどの短いピアノ曲に、1957年から60年までの4年の歳月をかけられた先生の仕事ぶりは、ちょうど私自身の東京芸術大学作曲科の学生生活と重なり合って先生の身近にある幸運をえたために、昨日のように思い出すことができる。先生の師早坂文雄氏ゆずりの28段の大判の五線紙が、一段ずつバラバラに刻まれて、今日の出版楽譜(音楽之友社 昭和39年)に見られるようなカリグラフィーの楽譜の断片が、机の片隅に沢山置かれていた。その時の私には、それらがどのような意味を持つのかさっぱり理解できなかったが、現在ならば多少の見当はつく。先生の表現したいもの、それを<純粋な生命力>と先生は言語化されたのだけれども、その<純粋な生命力>を表すための音組織として、例えばC−#C−Dのような3音ずつのクラスターを選択し、その3音クラスターの配列と組合せのありようを、その時、一つ一つ検討されていたのだと思う。12音の中には3音のクラスターが4つ作られ、音の順序性の観点から3P3×3P3×3P3×3P3=1296通りの配列が生じる。そしてこれらの配列は、3通りの移高が可能である。恐らく先生は、これらの配列を、垂直的にも水平的にも全部自分の耳で吟味された上で、選択と構造化の仕方を決定されたのであろう。この辺の事情を湯浅譲二氏は、「システムといういわゆる合理的な方法を、その極限まで追求して、その結果、遂には、佐藤慶次郎という人間の感性とまさに合一せしめてしまう」(佐藤慶次郎個展 The
Joy of VIbration 銀座南画廊 1974年プリグラム・ノート)と述べたのであった。けれども湯浅氏の言とは逆に、私には、先生の中にはまず表現するべき世界への直感が存在して、その世界へ到達するための最善の方法を吟味する過程で、ぼう大なノートの断片が残されるというのが実際ではないかと、観察されるのである。このことを武満徹氏は、「佐藤が音楽に求めた純粋性は、結局、詩とか音楽とか、一見純化された様式を通しては実現されないものであることが、私は自分のことのように理解できるのである」と述べたのだと思う。しかし、詩とか音楽とかを通しては実現されない純粋性とは何であろう。先生はカリグラフィーで、ヒューエル・タークイが、「モーツァルトのペダルのない響き、ブラームスのオルガン風の和声、バルトークやプロコフィエフの打楽器性とならべて、佐藤の思いつきに富んだペダル指示をもつハミング・ピアノ」と述べたような新しい響きを創られた後は、幾つかの作品を残されたのみで音楽の世界からエレクトロニック・モービルの世界へと、住処を移してしまわれた。そしてそこでは次のように述べておられる。興ノオモムクママニ作ラレタオブジェ達。コレラニオケル素子ノ単純ナ運動ガ、私ニトッテ面白ク、ソレラノ各々ガ愛スベキモノニ感ジラレルノデ、他ノ人達ニモ見テモライタイトイウダケノコトデアル。……私達ノ周囲ニアッテ限リナイ親シサヲ示シ、黙シタママ、寂カニ光ヲ放ッテイル<物>達。もしここで、<素子>や<物>などの術語を<音>という術語に、見ルを聞クに入れ換えるならば、先生の志向する<純粋な生命力>が少しは説明されることになろうかと思うのであるが……。 |
エレクトロニック・モビール作品
 |
 |
 |
||
沈黙のカルテット |
S.58.8月/佐藤和子氏
撮影 |
「お手玉」に見入る少女ち/佐藤和子氏撮影 |